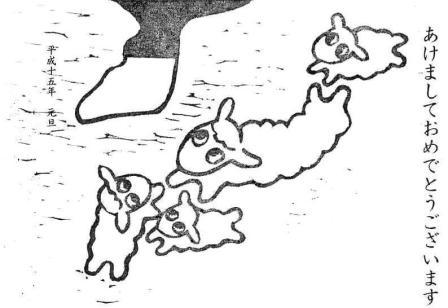����̑������L�� by �Ӓn��G����

�Q�O�O�V�����@�@�Q�O�O�U�N�@�@�����Q�O�O�T
|
| �P�Q���Q�Q���i���j�������Œx�� |
 |
�����S�N�A�����D�����ʂ��������q�N
���߂łƂ��I |
�����������̂��A�I舂ɂ��m��Ȃ������B���̓��{���y�R���N�[���i�ƌ������m�g�j�����R���N�[���̕�������݂�����j�ŋ��q���i���˂�������j�N���D�������Ƃ́B�����m�g�j�a�r�����ŏ��߂Ēm�����B�����P�����ȏ�O�̂��Ƃ��������B��ʂR�l�̖{�I�ł̉��t��S�����������A�y��̖�A�Z�p�̈��萫�A���y�I�ȉ��߁A�������A�ǂ���Ƃ��Ă��_���g�c�P�ʂł��邱�Ƃ͒N�̖ځi���j�ɂ����炩�������B�ނ͂S�N�O�̑O��ɂ����Z���ŎQ���������Q�ʂ��l�����Ă���̂����A�|��ɓ��w���Ă��猻�݂͖k�h�C�c�����[�x�b�N����̃U�r�[�l�E�}�C���[�̉��Ō��r��ς�ł���B�O��̐�J���ʂ������߂ɂ͗D�������Ȃ��B�z����₷��v���b�V���[�������낤�B�E�C�Ǝ��͂����˔��������ɑ債���N���B����艉�t�≹�y�ɑ���Ђ��ނ����ƌ������ɍD�������Ă�B�y��̓C�f�A���ł͂Ȃ��A�v���X�e�[�W�̂悤�Ɍ������̂��l�ɂ͗B��C�|����ł͂��邪�A�A�A |
| �P�Q���P�V���i���j���̂������J�̂����� |
���N�́u���v�̉̔��͊|��s�̓쓌�A�����m�ɖʂ�����O��s�������B��O��s����كz�[���ŊJ�Â��ꂽ�u��O��s�a���R���N�L�O�R���T�[�g�v�ɌĂꂽ�̂��B��N�̓�����Őf������A�|�I�P�Ƃ��Ă��Q�l�v�����܂߂Q���Ԃ̏o�����t�ƂȂ�̂ł���Ȃ�̔�p��������A��O��s�s���̌㉟���������Ă���Ȃ藹�����ꂽ�B��N�̔��Ȃ܂��A���N�ɓ����Ď������悤���܂˂Łu�_�v���쐬���A�זڂɂ��đo�����ӂ̏㏀�����i�߂�ꂽ�̂ŋC�����悭�{�Ԃ��}���邱�Ƃ��o�����B
��O��ɂ͕�̂ƂȂ鍇���c���������킯�ł͂Ȃ������悤�����u�I�[�P�X�g�����o�b�N�ɑ����̂����v�ƌĂт������Ƃ���P�T�O�l�߂��W�܂����Ƃ�������������B�h�C�c��͂�����������߂ĂƂ����l���قƂ�ǂ������̂ŁA�ʎZ�R�T����̗��K���d�˂��������B�܂����O�������������B�����͂P������̂��肾����������Q��ɂ��ė~�����ƌ����A���̗��R�������˂�ƂP��̉��t��ł͒��������l�����肫��Ȃ�����Ƃ̂��ƁB�܂����Ǝv�������A�����T�O�O�̍��Ȃ͂ǂ�������Ȃŗ��������o��قǂ̐����Ԃ�B�|�I�P�����̔M�ӂɉ����ė͂̌����s�����A��̖{�Ԃł͋Ȓ��Ɏv�킸���肪����قǂ̐���オ�肾�����B
���N�͑�������O��s�̓��A�g�c�����琺���|�����Ă��āA�y���ɂ͉ԑ��܂œ͂��Ă����B�m�o�n�Ƃ��Ă͂��肪�������肾���A����قǁu���v�i�̑�S�y�͂����j�������鍑���͑��ɂ͂���܂��B��������������A����������t���Ċ����B����������O��s�u�����̂���v���s�ψ��������A�̒��Łu���N�ȏ�ɂ킽���Ă킯�̉���Ȃ��h�C�c��Ɗi�����܂����v�ƌ���Ă�������ǁA�|�I�P�̃`�F���p�[�g�̒��Ɉ�l�h�C�c�l�̃g���������̂�m���Ă����̂��낤���B
 |
| ���V���P�Q���P�W���t�������@�i�w���F��@����j |
|
| �P�Q���W���i���j�܂肾���g���� |
 |
| ���N�����͒��g�A�X�����A���ł��� |
�x�g�W�̏o�����̃\�����炵�đS�R�Ⴄ�̂��B�o�Ȃ̂ɂ���Ȃɏ_�炩���g����������Ē������Ă���\�����o���������Ƃ͂Ȃ��B�������R�y�͂�����Ȃ����B�Ō�̃n�C�f���I�y���V�e�B�̍����V��ɗn�����ނ悤�ɏ����Ă������B�\�������ł͂Ȃ��B��������L���Ŗ��Ăł���Ȃ���e�a���ɕx�݁A�t�@�S�b�g��z������I�[�{�G�ƃo�����X�ǂ����Y���A�NJy��Z�N�V�����S�̂̐ڒ����Ƃ��ău�����h���ꂽ�▭�ȃn�[���j�[�������o���Ă����B
�O���u�c���v���đ�t�@���ɂȂ����Ƃ����z���c�̉Y�����Y�q���Ƃl������Ɗy����K�˂��B���N�����Ƃ͔ѓc���y�Ոȗ��R�����Ԃ�̍ĉ�������A�o���Ă��Ă���ĊJ����ԁu�ߓ��͏����ȃv���[���g�����肪�Ƃ��v�ƌ���ꂽ�B���͐�̃h�C�c���s���Ƀ}���n�C������ɗ�������Ď�q����Ɂu�~�j�E�n�[���j�J�v�����N�������ɓn���Ă����悤����ł������̂��B�i���݂Ɏ�q����̖��O�̓V���[�}�b�n����B�e�P�h���C�o�[�̐^��������Ɓu���̒ʂ肾�v�Ə��Ă����j�B�m���g�n�E�[���̂j������낵���ƌ����Ă܂����Ɠ`����Ɓu�����A�j���͎��X�Ƃɂ��������݂ɗ����B�ނ̓}�E�X�s�[�X���R�����Ă��Ăˁ[�v�����āB
 |
| �q��iner Muller van Recum ���E���̖ѕM�T�C�� |
���N�����͍���A�~�X�^�[�r�Ƃ��ē��{�Ő��Ȑl�C���ւ�X�N�����@�`�F�t�X�L�[���w������A�U�[���u�����b�P�����������y�c�̃x�[�g�[���F�������ȃ`�N���X�łU�A�V�A�W�A�X�Ԃ𐁂��A�O���̂T�Ȃ͂�����l�̎��Fritsche�����������̂��������B�uFritsche����͂����������^�C�A�����ł���H�v�ƕ����Ɓu�ڂ����ˁ[�v�u�j���������Ă���܂����v�u�͂͂�A�͂�قǁv�B�����łl����̃X���h�C�����݁B�u��������Ƃ�����l��Ȃ���c�������ł����H�v����ɑ��Ắu��������͂Ȃ����낤�B���͋߂����ɂ�����̃I�[�P�X�g���ƍ�������B�����Ȃ�ƃN�����l�b�g�Z�N�V�����͂T�l�ɂȂ����Ⴄ����A�A�A�v�B�h�C�c�ł͈ˑR�I�[�P�X�g���ĕ҂̓����������Ȃ悤���B�u���l�ɂȂ낤�����Ȃ����x�X�g�ł���I�v�ƌ����Ɓu����͖l�ɂ͕�����Ȃ����ǁv�Ƃǂ��܂ł��T���߂Ȃ����ł���B�u���N�܂��ѓc�ʼn�܂��傤�I�v�ƈ��肵�ĕʂꂽ���A�T�C���y���̂��肪�Ԉ���ĕM�y���������Ă��Ă��܂����̂łb�c�Ƀ��N����̖ѕM�T�C������������B���N�����������ł����Θa�̌͘I�`���u�z�[�����C�h�E�W���p�j�[�Y�E�h���C�t���[�c�v�ƌ����ăv���[���g�������A�����Ƌ������悤�Ɏ������ĐH�ׂ����낤���B |
| �P�Q���S���i���j�z���o�ĂĂ����� |
 |
| ��R�̃��R�[�_�[���ԂɈ͂܂�� |
�����͓��Ђ̃��R�[�_�[�v�҂x������̒�N�s�s������B�l���A�N�g�V�e�B�[���z�e���I�[�N���̉��͓�������삯���ė����l���܂߂V�O�l�ȏ�̎Q���҂łӂ���オ�����B���ꂾ���ނƂ̕ʂ��ɂ��ސl���W�܂����̂��x������̐l���̎������낤�B
�x������ƍŏ��ɏo������̂͂��ꂱ��R�O�N�O���B�l���{�Љc�Ƃŋ���p�y���S�����Ă����V�N�̊Ԃɂx������Ƃ͖{���ɗǂ��d�����R�����Ă�������B�v���X�`�b�N�E���R�[�_�[�̑S�ʃ��f���`�F���W�A���y�N���X�ؐ����R�[�_�[�̊J���A�ؖڍ����`�a�r���R�[�_�[�̔����A�o���b�N�s�b�`�̃f�i�[���f���̔����A�������Ў胊�R�[�_�[�̊J���B
�������R�[�_�[�J���e�b�g�A�����搶�A�g�D�l�����f�A�P���u���b�W�E�o�X�J�[�Y�A�N�i�C�X�A�n�E���F���Ƃ̌𗬁B
����ɓ�l�Łu���R�[�_�[�̖{�v�Ƃ������j�[�N�Ȃo�q���s�����B�����̓��R�[�_�[�̒f�ʐ}���H�����Љ����A�������t�Ƃ̃C���^�r���[�Ȃǂ��ڂ��Ă������A�i�X�Ɠ��e���G�X�J���[�g���āA������ł͓��{���̖��������ȉƑS���ɃA���P�[�g�𑗕t���A���R�[�_�[�ɂ��Ăǂ��v�����A��Ȃ������Ƃ͂��邩�A��Ȃ������͂��邩�A�͂Ȃ���Ȃ��Ȃ��̂��A�ȂǂƂ��ƍׂ�����������ɂ�����ꗗ�\�ɂ��Čf�ڂ����肵���B��C�̎���Ƃ��������悤���Ȃ��B���́u���R�[�_�[�̖{�v�͂Q�R���܂ő��������l�̓]�ɔ����Ď��R���ł����B���ł����̃o�b�N�i���o�[��厖�ɕۊǂ��Ă���l�����邻���ł���B�x������͊ԈႢ�Ȃ����{��ƌ����ėǂ��m���ƃ��R�[�_�[����̘r�������Ă���̂Ɍ����Ě��炸�A���l������A��Ɍ����ŁA�S�ꉷ�����S�̎�����ł���B�S�������̐��i�̖l�͂x������l�Ԃ̗D��������ł��邱�Ƃ̑�����w���Ă�������B�ǂ������܂ł��x������̂܂܂ł��Ă��������B���肪�Ƃ��B�S����̊��ӂ����߂āB |
| �P�P���Q�W���i�j�P�O�����{���݂̗z�C |
 �l�e���ł��B�p�p�����炭�V���̍L���Ɩl�̊������ׂĂ���p�\�R���Ɍ������ăC���^�[�l�b�g�ʼn����n�߂����ɉ����C���[�ȗ\����������ł��B��������u�ق�e���A���Ă݂�A���O���ڂ������v�����āB�������Ǝv���ăp�\�R����`�����牽�Ɓg�䂪�Ƃ̂ق��ƃP���E�t�H�g�R���e�X�g�h�Ƃ����y�[�W�ɑ�R�̌��̎ʐ^�ƕ���Ŗl�̊�ʐ^������ł͂���܂��B�݂�Ȗѕ��݂̂悳�����ȉ������~��������Ȃ̂ɖl�����G��ŕ����Ȃ�������Ă��܂��B���������̌��̃^�C�g�����u���U����D���v�Ƃ��u�k�N�k�N�����Q�v�Ƃ��u���������ā[�v�Ƃ��Ȃ̂ɖl�̂́u�N�ɂ�����Ȃ��b�v�ŁA�l�̐��������܂Ŗ\�I���Ă��ł���[�B������Č����N�Q�ł���ˁH��ꂱ��ȈÂ��b�����I����͂��Ȃ�����Ȃ��ł����B���H����܂����������D���ȕ���������t�H�ׂ����Ă������āH�ق�ƂɁH�ق�Ƃɂق�ƁH����[�A�l�̎ʐ^�ɂ����E�̃R�����g�������Ă������`���Ihttps://hotlemon.jp/entries.html�̂Q�V�����̈�Ԃ�����̕��Ł[���B �l�e���ł��B�p�p�����炭�V���̍L���Ɩl�̊������ׂĂ���p�\�R���Ɍ������ăC���^�[�l�b�g�ʼn����n�߂����ɉ����C���[�ȗ\����������ł��B��������u�ق�e���A���Ă݂�A���O���ڂ������v�����āB�������Ǝv���ăp�\�R����`�����牽�Ɓg�䂪�Ƃ̂ق��ƃP���E�t�H�g�R���e�X�g�h�Ƃ����y�[�W�ɑ�R�̌��̎ʐ^�ƕ���Ŗl�̊�ʐ^������ł͂���܂��B�݂�Ȗѕ��݂̂悳�����ȉ������~��������Ȃ̂ɖl�����G��ŕ����Ȃ�������Ă��܂��B���������̌��̃^�C�g�����u���U����D���v�Ƃ��u�k�N�k�N�����Q�v�Ƃ��u���������ā[�v�Ƃ��Ȃ̂ɖl�̂́u�N�ɂ�����Ȃ��b�v�ŁA�l�̐��������܂Ŗ\�I���Ă��ł���[�B������Č����N�Q�ł���ˁH��ꂱ��ȈÂ��b�����I����͂��Ȃ�����Ȃ��ł����B���H����܂����������D���ȕ���������t�H�ׂ����Ă������āH�ق�ƂɁH�ق�Ƃɂق�ƁH����[�A�l�̎ʐ^�ɂ����E�̃R�����g�������Ă������`���Ihttps://hotlemon.jp/entries.html�̂Q�V�����̈�Ԃ�����̕��Ł[���B |
| �P�P���Q�S���i���j�������V�C�ɂȁ[�� |
| �F����͂����Q�O�������́u�p�C�p�[�Y�v304����ǂ݂܂������H�u�z���c�̉�in�h�C�c�v�Ɩ��ł����j�����̋L�������J���Ŋ����������Ă��܂��B���ꂩ������Q�������o�߂��悤�Ƃ��Ă��܂����A�L����ʐ^������Ƃ��̎��̋�C��������̂��Ƃ̂悤�ɑh���Ă��܂��B�����̘^���R�Ȃ�V�݂����v���t�B�[�����u���݂݂悲���v�ɃA�b�v���܂����B��̃T�����[�h�b���R�[�_�[�̓����}�C�N�Ř^�����̂ʼn��͗ǂ�����܂��A���t�̔M�C�Ɖ��̉��������͋C�͏[���ɓ`����Ă��܂��B�Ȃ��A�������ɂٍ͐e���f�ڂ����\��ł��B�~�x�݂̂Ђ܂Ԃ��ɂ��ǂ݉������B�����ƁA���ꂩ��z�[���y�[�W�E�r���_�[���u�V����u�P�O�Ƀ��@�[�W�����E�A�b�v������u�e�X�g�v�쐬�@�\���lj�����Ă����̂Ŏ����ɍ���Ă݂܂����B�ܕi�͂���܂���A�������炸�B |
| �P�P���P�X���i���j�ߌォ�珬�J |
 |
| �ܗ��m�[�X�E�B���O�ɂĐڑ������� |
���̏T���͖����k�`�m�ɒ��킵���B�����������o�C���p�\�R�������̂����牮�O�ł��C���^�[�l�b�g������Ă݂����Ƃ����A�������ꂾ���̗��R�ł���B���Ƃ��ƃ��b�c�m�[�g�v�T�̃p�b�P�[�W�ɂ́u�����k�`�m�ڑ��K�C�h�v�Ƃ����p���t���b�g�������Ă��āA��������l�͓��R�����k�`�m�������̂Ƃ���A���А��������[�^�[�̐����i�ԂƂƂ��ɐڑ��̂̎d���܂ō��ؒ��J�ɐ}�����Ă���̂��B�������̓p�\�R�����s�Ȃ̂Ő����Ɩ������̂����A�����i�̃o�b�t�@���[�u�G�A�E�X�e�[�V�����v�̃p�b�P�[�W�ɂ��₽��Ɓu�ȒP�ݒ�v�̕���������Ă����̂Ő��ɔ����Ă��܂����B�Ƃ��낪�����͊ȒP�ɖ≮�������Ȃ������B�o�b�t�@���[�̐����ɂ��·@���f���ƃG�A�E�X�e�[�V�������k�`�m�P�[�u���łȂ��A�A�p�\�R���ɕt���̂b�c�|�q���Z�b�g���āA�B�`�n�r�r�{�^�����s�b�Ɖ����A�n�C�ڑ������I�Ƃ̂��ƂȂ̂����A�S�R�������Ȃ��̂��B�p�i�\�j�b�N�̑��k�����ɓd�b�������ĉ��ɏo���j���Ɏ�����������Ƌ����̓������Ԃ��Ă����B�u�`�n�r�r�̓o�b�t�@���[����Ǝ��̋K�i�ł��̂œ��Ђ̃p�\�R���͑Ή����Ă���܂���v�B�u���H�I���ች�Ő����@��Ɏw�肵�Ă�I�v�ƌ�C�����߂�Ɓu���ӌ��͊J���̕��ɐ\���`���Ă����܂��v�����āB�����閳�ӔC�B�S���łǂꂾ���̃��[�U�[�������Ă��邱�Ƃ��I�d�����Ȃ��̂ł��ꂩ��蓮�Őݒ��Ƃ�i�߂����A�o�o�o�n�d���̂r�r�h�c���̂`�d�r���̃`���v���J���v���B�����s���ʂĂ��Ƃ���ł܂��p�i�\�j�b�N�̑��k�����ɏ��������߂�ƁA���x�͏����̒S�����o�Ē��J�Ƀ`�F�b�N�|�C���g�������Ă��ꂽ�B���߂Ė����łȂ��������ɂ͐������m��Ȃ����̒S���҂����_�̂悤�Ɏv�������̂��B�����p���Ȃ��̂ɖ����̃z�b�g�X�|�b�g������u�ܗ��v�ɍs���ăC���^�[�l�b�g�ɐڑ����Ă݂��B���[�āA���ꂩ�炱�̖����k�`�m�ʼn�������̂����l���悤�B |
| �P�P���P�T���i���j�������� |
 �N�Ɉ�x�̑S�����ł���u���R���t��Q�O�O�U�v���߂Â��Ă����B���T�Q�T���̓y�j���A�ꏊ�͍P��̉��l�����̈�فB�S�����͑������̂ō��N�łT��ڂ��B����͂Q�O�O�Q�N�A�Y����NK�z�[���ɂU�O�O�l�̘V��j�����W�܂��đ升�t���J��L�����B���̊������S���ɔg�y���đ��̍��I�ɒn�����J�Â����悤�ɂȂ�A�k�͖k�C�������͋�B�܂ŁA���݂܂łɂP�O�O��ȏ�A��Q���T��l�̉��Q���Ґ��𐔂���Ɏ����Ă���B�������݂̉��l�Ɉڂ����u���R���t��Q�O�O�R�v�ł͎Q���҂���l�ɒB�������̂́A���̌�u�Q�O�O�S�v�͂W�O�O���A��N�́u�Q�O�O�T�v�͂T�O�O���ƁA��⌸���Ă��Ă���̂͂��т������肾�B�n�������ꂾ������ɂȂ��Ă���A�킴�킴���l�܂ŏo�|���čs���K�R���������Ƃ������̂��낤�B �N�Ɉ�x�̑S�����ł���u���R���t��Q�O�O�U�v���߂Â��Ă����B���T�Q�T���̓y�j���A�ꏊ�͍P��̉��l�����̈�فB�S�����͑������̂ō��N�łT��ڂ��B����͂Q�O�O�Q�N�A�Y����NK�z�[���ɂU�O�O�l�̘V��j�����W�܂��đ升�t���J��L�����B���̊������S���ɔg�y���đ��̍��I�ɒn�����J�Â����悤�ɂȂ�A�k�͖k�C�������͋�B�܂ŁA���݂܂łɂP�O�O��ȏ�A��Q���T��l�̉��Q���Ґ��𐔂���Ɏ����Ă���B�������݂̉��l�Ɉڂ����u���R���t��Q�O�O�R�v�ł͎Q���҂���l�ɒB�������̂́A���̌�u�Q�O�O�S�v�͂W�O�O���A��N�́u�Q�O�O�T�v�͂T�O�O���ƁA��⌸���Ă��Ă���̂͂��т������肾�B�n�������ꂾ������ɂȂ��Ă���A�킴�킴���l�܂ŏo�|���čs���K�R���������Ƃ������̂��낤�B
�����A�V�����Ⴋ���A��肢��������A�v�����A�}���A�a�y����m�y����A�����ăG�[���[���x�[�����A�݂��ɗ͂����킹�₢�����ĉ��t������y�������A���l������{���ɁA�ہA���E�Ɍ����Ĕ��M�������A�܂��A�o���邱�ƂȂ�T�C�U�N�O�Ƀo���N�[�o�[�Ŏ������ꂽ�Ƃ����U�C�T�O�O�l�̑升�t�M�l�X�L�^�����l�œh��ւ������Ɗ���Ă���B���̋L�^��j���̂͐��E�L���Ƃ����ǂ��A���y���琅�������Δ����č������{�������đ��ɂȂ��ƐM���Ă��邩��B�u���R���t��Q�O�O�U�v�ɋ��������������������������Bhttp://www.yamaha.co.jp/jiyuuensoukai/concert/2006.html
�����G�[���[�������ĎQ�����܂��B���Ȃ����Q�����Ă݂܂��H
|
| 11��7���i�j������ |
�ˁ[�ˁ[�A�����́u�������[�c�@���g�v�ς��H����̗\���ŃV���^�b�g���[�i�ԑg�ł̓V���^�[�h���[�j�����Ƃ�������y���݂ɂ��Ă����ǁA�b�̓U�r�[�l�E�}�C���[�̑�Q�y�͂̉��t���o�b�N�Ɂu�N�����l�b�g�d�t�ȁv�̘b����V���^�b�g���[���l�Ă����o�Z�b�g�N�����l�b�g�̘b�Ɉڂ��āE�E�E�����ň�u�o�Z�b�g�N���𐁂��t�҂̃J�b�g�����������ǁA����̓��H���t�K���O�E�}�C���[�������悤�ȁE�E�E�Ȃ����������̂Ƃ������P�����O�ɍs��������̃o���x���N�̊X���݂��f���o���ꂽ�B
�u���̊X�ɂ̓��[���b�p�ł������Ȃ��o�Z�b�g�N�����l�b�g�̍H�[������v�Ƃ����e���b�v�����ꂽ���Ǝv���Ǝ��ɉf���o���ꂽ�͉̂��ƃZ�Q���P����I�M�S�Ɋy������莎�t�����肷��f�������\�����Љ��Ă����B
�m��Ȃ������[�BNHK����ނɗ����Ȃ�Ęb�S�R���ĂȂ��������B�������{�ŕ������ꂽ���Ƃ�m���Ă���̂��낤���H�Z�Q���P����͋߁X���{�ɉ��t���s�ɗ���͂�������摜���v�����g�A�E�g���ăv���[���g���悤�B
|
| 11��2���i���j��������H�߂� |
 |
| ���F��MINI�J�[�R���N�V���� |
MINI�����߂Ă̎Ԍ�����A���Ă����B�f�f�̌��ʂ͂������Č��N�̂������ł���B����3�N�o�Ƃ����̂ɂ܂��V���C�����������A�������璭�߂Ă��߂��Ɋ���Ă��A�Ȃ�ăJ�b�R�����낤�I�ƓƂ�x�ɓ����Ă��܂��B�ŋ߂͓d�Ԓʋɂ����̂ŏT���ȊO���܂肩�܂��Ă������Ȃ��̂����킢�������B���т��тƂ悭���邵�A�����͂܂�4��Km���炸�����R������b�^�[�P�RKm��������Ƃ͂Ȃ��B�m���Ƀg�����N�͋������A�����ƂȂ�Ό�Ȃ�|���邩��A���܂Őς݂����Ă��ς߂Ȃ������Ƃ����o���͂Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��A���g�ɒm�b������Ă���Ƃ������A���̕K�v�ɂ��ď[���ȃR���p�N�g�������̃N���}�̌����Ȃ̂��B�ŋ߂͂��̊|��ɂ����Ԃ������Ƒ����Ă����B�V���o�[��b�h�͕��}�����A�O���[����u���[�͂ƂĂ����ꂢ�����A�y�b�p�[�E�z���C�g�Ƃ��������f�G���B�����A�Ȃ�ƌ����Ă����L�b�h�E�C�G���[�ق�MINI�Ɏ������F�͂Ȃ��낤�B�ڗ����Ƃ��̏�Ȃ����ǁA������ɕi�̂悳������B���̖��͓I�ȐF�����N�̃��f������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ�������������B�����Ɣ���Ȃ������낤�ȁB�ǂ����l�̍D�݂͂����}�C�m���e�B�炵���B |
| 10��22���i���j�[�����珬�J |
 |
| �����j���[�J�}�[�̃p�i�\�j�b�NW�T�B�Ƃɂ����y���B |
�O�X���璲�q�����������m�[�g�p�\�R�������悢��C�����@���邱�ƂɂȂ����B�Q�C�R�x���J�o���[DVD���g���ăZ�b�g�A�b�v�Ƃ����J���t���܂𒍓������̂����A���̒���͑h��������̂̏��X�ɂ܂��Ǐ������Č��ɖ߂��Ă��܂��B�ŋ߂͊��S�ɗ����オ��܂łɂP���Ԕ���v���A�����̕ϊ��ɂP�����|����Ƃ����L�l�������B�E�B���X��X�p�C�E�F�A�̃`�F�b�N���s���Ă��������o����Ȃ��B���ł̓d�b�T�|�[�g�Z���^�[�̒S���҂��Ƃ��Ƃ������グ�Ă��܂����B�����ꂱ���Ȃ邱�Ƃ�\�z���Ď��Ȃ�p�\�R���I���Ƃ��J�n���Ă����̂����A�Ƃɂ��������^�тł��鏬�����Čy���ăo�b�e���[��������������̂Ƃ�����őI�̂��p�i�\�j�b�N�̂P�Q�D�P�^W5�ł���B�����덡�N�S���̔��������A���E�Ōy�ʂ̂P�P�X�X���Ńo�b�e���[�͂P�T���Ԏ��������B����܂ł̃_�C�i�u�b�N�͂P�T�^�łRKg�ȏ゠��A�o�b�e���[���Q���Ԃ��������Ȃ������B���̎�̘b�Ƃ��Ĕ@���Ɏ������������������Ƃ��������b�������̂����A�l�̏ꍇ�́AOffice���C���X�g�[������ĂȂ��@��A���f���`�F���W���O�̒l�����A�v���o�C�_�[�ύX�ɂ����T�ȂǂŎs�����P�O���~�ȏ�����������Ƃ��ł����B�������g���n�߂����肾���������[�e�ʂ�CPU�̐��\���オ���Ă��邱�Ƃ�������ɉ��K�ł���B����W5���g���Ă��낻��h�C�c���s�̐������n�߂悤�B |
| 10��16���i���j |
| �����ꕔ�Ɍ��J�̊�]���������G�[���[�ɂ��{�����E�\������������UP���܂����B�ق�Ƃɓ��{�����H�I |
| 10��9���i���j���{�͏��� |
 |
 |
�o���x���N�ɂ������ς��
���F��MINIONE�l�s�T�����[�t�t�� |
�h���X�f���Ō�����
���Ƃ̈╨�g���o���g |
�P�O���Ԃɋy�ԃh�C�c���s���疳���A���B�h���X�f���A�o���x���N�A�}�C�j���Q���A�j�������x���N�A�n�C�f���x���N�A���ꂼ��Ɋy�����v���o��M�d�Ȍo��������������ǁA�h���X�f���ɂ�����DKG�N�����l�b�g�E�A���T���u���ƍ����ʼn��t�������C���x���K�[�̃p�b�T�J���A�͋F��Ƃ������ׂ������I�ȋ����������B�܂����z���Ԃ��Ă��S���k����̂́A�}�C�j���Q���̔����قł��̃~���[���t�F���g�̃N�����l�b�g�����̎�ŐG��邱�Ƃ��ł������ƁB������Z�Q���P����S���c�ْ��̈������̍D�ӂƋ@�]�Ƃɂ���Ă����炳�ꂽ���ʂ������B���t�͕s�[���ł����y�Ƃ������ʂ̌���ɂ���ĐS��ʂ킹�邱�Ƃ��o����B���炽�߂Ă��̐^�����m�F�ł������ł��������BVielen
Dank!!! |
| 9��27���i���j���J |
 |
| �ו��͂����� |
���悢��h�C�c�Ɍ������Ĕ����܂��B�A������̂͂P�O���X���B�z���c�̉�̃����o�[�ƃh���X�f���Ńh�C�c�E�N�����l�b�g�E����̃V���|�W�E���ɎQ�������t������A�o���x���N�Ɉړ����ăZ�Q���P���̈ē��ŃN�����l�b�g�H�[�Ȃǂ����w����\��B
���ꂩ��͈�s�ƕʂ�ăg�[�}�X�E�N�b�N�̎����\��Ў�Ƀj�������x���N��n�C�f���x���N�Ȃǂ�����Ă��܂��B���Ƀo���x���N���烍�[�J�����ɏ���ă}�C�j���Q���̔����قɈ��u����Ă���H�~���[���t�F���g�̃N�����l�b�g�����ɍs���̂��n�C���C�g�̂ЂƂł��B����̗��łǂ̂悤�ȏo��┭��������̂��ƂĂ��y���݂ł��B�����A���Ă��ꂽ��F�X�ƕ��܂��B�ł́A�s���Ă��܂��B |
| 9��15���i���j����₩ |
 |
|
���b�X�����������b�ɂȂ����l�̑�ȉ��y���Ԃ���
|
�J�[���E���C�X�^�[�̃��b�X������u�����B�ꏊ�̓C�V�����̒n���X�^�W�I�B�Ȃ̓��[�K�[��B-Dur�̃\�i�^��P�y�́B�s�A�m�͂P�O���̉�ʼn��������t�����肢���Ă���Ok����ɁA�ʖ�̓z���c�̉��Yk����ɂ��肢�����B
���C�X�^�[�͌����܂ł��Ȃ��鉤�J������������x�������t�B���������̕s���̎�ȑt�ҁB���̑S����ɘj�銊�炩�ŏ_�炩�ȉ��F�ƌ������ؗ�ȃe�N�j�b�N�͑��̒ǐ����������A���E���̃N�����l�b�g�t�҂̏^�ƑA�]�Ɠ��ۂ̓I�������B���C�X�^�[���ăN�����l�b�g���n�߂���h�C�c�ǂɋ������������肵���l�͓��{�ɂ�����������ɈႢ�Ȃ��B�z���c����̒��ɂ����[���A�h���X��leister�Ƃ����l�����邭�炢���B
 |
| �����p�������{����D�������� |
�v���Ԃ����C�X�^�[�̖���m�����̂͑�w�Q�A�R�N�̍��������B�m���w�ɎQ�������܂�ď��߂ĊC�O�ɍs�������A�p���̃��R�[�h�X�Ń��C�X�^�[�̃f�r���[�łł���E�F�[�o�[�P�Ԃƃ��[�c�@���g�̋��t�Ȃ��J�b�v�����O���ꂽLP���R�[�h�����̂��B�Ȃɂ����{�Ŕ����������̂��A�����ƈٍ��̒n�ŕ����オ���Ă����̂��낤�B���������ăZ�[�k�쉈���̃g�D�C�����[����������Ă���Ɖ���牓������NJy��̉��F���������Ă����B�߂Â��Ă݂�Ɩ�O���y���̃X�e�[�W�Ŗ؊njd�t�c�����t���Ă���B���t�I����y�����։���Ă݂�ƁA�������N�����l�b�g�𐁂��Ă����������菵�����Ă��ꂽ�B�ނ̖��̓A���h���E�u�[�^�[���i��ɐԍ�B�O�����t���j�B�ق��p��Ŏ��ȏЉ�A�������N�����l�b�g�𐁂��Ă���Ɠ`����Ƒ�w���ł���āu���{�l�Ȃ�I�]�m��m��Ȃ����H�v�Ɩ��ꂽ�B���̎��͒m��Ȃ��Ɠ������̂����A���ꂪ��ɓ����Ō��������A�}�I�P�A�u�R���Z�[���E�����l�[���v��M�S�Ɏw���E�w�����Ă����������|��̍ז�i�����H�����Ȃ��j�F�����Ɣ��������B��l�͖������M�����h�E���s���u���P�[�k�E�I�[�P�X�g���̓����������������B
�u�[�^�[���͖l�̃��R�[�h�����Ă��̎������������̂��B�u�����i���C�X�^�[�j�͏�肢��B�����ƗL���ɂȂ�v�B����Ȗ�ł��̃h�C�c�E�O�����t�H���̉��F�����R�[�h�E�W���P�b�g�̒��ɂ́A�Ȃ����t�����X�l�̃A���h���E�u�[�^�[���ƁA���̎��t���[�g�𐁂��Ă����W�����E�s�G�[���E�����p���̃T�C���i�J�^�J�i�Ń����p���Ɓj�������Ă���̂ł��B�l�̂��R�[�h�̂P���B
���C�X�^�[�̃��b�X���͂V�O�߂��N������������Ȃ��o�C�^���e�B�Ɉ�ꂽ�����͂̂���f���炵�����̂������B���ɑ����̋����Ɣ����ɖ����Ă����B�������ĕ������̂����A�]��ɂ��������́A�^����ꂽ���̂������̂ł܂��[�������ł����ɂ���B�u��u���Ă悩�����v���ꂾ���͊ԈႢ�Ȃ��B |
| 9��3���i���j�H���� |
 |
| ����136�l�̐Ãt�B���E�|�I�P�����I�[�P�X�g�� |
�����ɂƂ��Ă�����Ƃ����n�[�h�������z�����Ƃ��̋C���͊i�ʂł���B���s�ψ��̈�l�Ƃ��Ĉ�N�O������ɎQ�悵�Ă�������̐Ãt�B���Ƃ̃W���C���g�R���T�[�g�͑听���������B���̊|��s���U�w�K�Z���^�[�z�[���̓L���p��t�̐�l�ȏ�̂��q�l�Ŗ��ȂƂȂ�A��3���̐Ãt�B���Ƃ̍������t�ł͂P�R�U�l���̗��y�c�����A�X�e�[�W����������ɕ��сu�Е����X�v�Ɓu�n���K���[���ȑ�T�ԁv��M���B�Ō�ɂ͂��̉��t�������s���|��s�����u���f�c�L�[�s�i�ȁv���w�����Ė��ꊄ������̑劅�т̒��Ŗ���������邱�Ƃ��ł����B
���t���e���|�I�P�A�Ãt�B���Ƃ��ɑf���炵�������B�Ãt�B���ɂ̓`�F�����P�O�l�A�R���g���o�X���U�l�����ĕ������[�������ቹ���������Ă������A���ꂼ�ꔼ���������Ȃ��|�I�P�ɂ͑A�܂������肾�B�NJy��̐������������ɍ����B���̈�_����q����ɂ��������ꂽ�B�y�[���M�����g�̕���ɒ��O���䂫���ޘb�p�͂������v���̏��D����ł���B
�|�I�P���́u�l�Z�}�����v�����������B�u�J���������z�ȁv�����t��������N�͂R��̍��킹�̊Ԃɂ��߂��߂��Ə�B���A�{�Ԃōō��̉��t���I���đ��ł��邱�Ƃ��ؖ������B��������͉v�X�Z�p�ɖ������|����Ɠ����ɂ�莩�R�Ŏ��R�ȕ\���͂�g�ɂ����悤���B�g�����R����e���t�Ԃ����h����g�t�Ԃ����̒e�������R���h�ɂȂ����Ɗ������B
���āA�l�ɂƂ��Ă̖��́u�{�����v�������B�}篂���������Ă����N�����l�b�g�̃\���͗J�T�̎킾�����B�{�ߏǂ͂��Ȃ�������Ƃ͌����A���̊W�ʼn����͔����́A���̉e���Ő�͊��ނ́A����ɍŋ߉E�ڂɕ����炢���ł��ĉ��������Â炢�͂̈��R���f�B�V�����ŗՂu�{�����v�������̂��B�Ă̒�A��T�ԑO�̍��t���K�ł̓����f�B�[�̓r����1���H���Ă��܂��卬���B�P�U���������ْ����炩���菬�w���X���[�Y�Ɋ��炸�S�R��������Ȃ��B�l���K�ł͈Õ��ł��ł���̂ɂ����\���ƂȂ�Əオ���ăC�[�W�[�E�~�X������B����Ȃ��Ƃ͍��܂łȂ��������Ƃ��B
�u�ŏW���͂��������̂��낤���H�v�u���̓I�ȋ@�\���ቺ���Ă���̂��낤���H�v�u���������ɂ̓\���͖����Ȃ̂��낤���H�v�ł�Ǝ��⎩���̈�T�Ԃ������B�p�[�g���ɉ��M�ōׂ������ӂ��������݁A�厖�ȉ��ɂ̓}�[�J�[�ŐF��h��A�O��I�Ɋy����]���ɏĂ��t���ĂЂ�����C���[�W�E�g���[�j���O�ɓw�߂��B���̍b�゠���Ă��A�Q�l�v���ł���ƃm�[�~�X�Ő����ʂ����Ƃ��ł��A�{�Ԃł͏����}�g��t���Ăقږ����̂������t�����邱�Ƃ��ł����B�u���Ƃ��F�ɖ��f���|�����ɂ��v�B�u�{�����v���t��̐S����̈��g���ƒB�����͑��l�ɂ͌����ĉ�����܂��Ǝv��ꂽ�B
�Ƃ��낪�A���t���̑ł��グ�Ńt���[�g�ƃt�@�S�b�g�̃\����S�������c���Ɋ��z���ƁA�ӊO�ɂ��A�u������x�Ƃ���ȋꂵ���v�����������Ȃ��v�A�u�S�����������яo�����炢�ْ������v�A�u�̖{�ԂŔƂ����~�X�̃g���E�}�ōŌ�܂ŋC���Ȃ������v�A�u���������悤�ɐ����鎩�M�͑S���Ȃ��v�A�Ȃǂƈٌ������ɋ�Y��f�I�����̂��B�ꌩ�����Ȃ��ɓ��X�ƃ\���𐁂��Ă���悤�Ɍ�����Ⴂ�c���B�����ꂼ��ɐl�m��ʔY�݂�����A�������������w�͂����Ă���̂��ȁ[�A�Ƒ傢�Ɋ��S���A�����ĈԂ߂�ꂽ�B
����Ă�����ʂ̃A���P�[�g�̒��Ɉꖇ�����u�N�����l�b�g�̉�����i�ł悩�����v�Ə����Ă���̂����A��������͂܂��������C�����߂��āA�悵�A���ꂩ����撣�낤�I�Ǝv�����̂ł����B�����Ă��ꂽ�P�U�˂̏��̎q�A�{���ɂ��肪�Ƃ��B
|
| 8��26���i�y�j�܂� |
�܂���j�������u�T���o�J�[�j�o���v�ɏo������ȂǂƂ͖��ɂ��v��Ȃ������B�Ȃ�����Ȃ��ƂɂȂ����̂��H�S�Ắu���R���t�� in
�É��O�����V�b�v�v�Ŗl�����ʑ��u���Y�ꂽ���Ƃɂ��B���̕��ʑ���s�b�N�A�b�v���Ă��ꂽ���R�搶�ƌ���d�b�łǂ��Ŏ�邩���k�����ۂɁu�Q�U���ɐŎ��R���t�����邩�炻���œn����v�Ƃ������ƂɂȂ����B���X�����ɏW���ꏊ�̐Y�Ɩf�ՃZ���^�[�ɍs���ĕ��ʑ�����A���X�ɑގU���悤�Ƃ������ς��肾�����̂����u���ʑ�̓N���}�̃g�����N�ɓ����Ă邯�Ǎ��n���Ɖו��ɂȂ邩�玩�R���t��I����Ă���ł�����ˁv�Ɛ��R�搶�B�ǂ����l�����R�Q������Ǝv���Ă�����Ԃ�Ȃ̂��B�u���H���́[�A�܂��A�A�v�ȂǂƞB���ȕԎ������Ă�����ɐl�͂ǂ�ǂ�W�܂�A���͂ǂ�ǂ�i��Ŕߌ��̖����J���Ă��܂����B�l�ɂ͍R���Ȃ��^���Ƃ������̂�����̂��B
 |
 |
| ���������瑱�X�ƏW�܂�Q���ҒB |
�T���o�J�[�j�o���Ȃ�ł͂̕��͋C |
�u�ŁA�����͉������t����́H�v�ƃX�^�b�t�̈�l�ɕ����Ɓu�R�Ȃ��J��Ԃ����������Ȃ̂Ŗw�ǂ̊F����͈Õ��ł��B���ꂪ�N���̊y���ł��v�ƌ����č����o���ꂽ�Ȃ́u�������������v�u���̃J�[�j�o���i�ʏ́F���J�j�j�v�Ə����uA
Vos do
Morro�v�B�Q�Ăċ߂��̃R���r�j�ŃR�s�[���A�K���Ŋy���ɒ@�����ށB�������Q�W���߂́u�`�������������������v�ł�������ƈÕ������ʂȂ̂ɁA�T�o���̊y�������n�[�T���܂ł̂P���Ԃʼn�����Ȃ�ē��ꖳ�����B�M�u�A�b�v����Ȃ獡�����Ȃ��ȁA�ȂǂƎv���Ă�����ɋ߂��̋n�Ń��n�[�T�����n�܂����B�悸�͉��t�̂݁B�l�����y����n�ʂɒu���ăJ���j���O����̂����A���s�[�g��_���Z�[�j����_�J�[�|�������Ăǂ�������Ă���̂��`���v���J���v���B���̒����卬���̂܂܍��x�͍s�i�̗��K�B�T���o�̃��Y���ɍ��킹�ēJ�̍��}�ʼn��ɓ�������N���N���������B����Ȃ��Ƃ���̒��w�̃t�H�[�N�_���X�ȗ����ȁ[�A�Ɠ��̋��Ŏv���B�܂��A�s�i���Ȃ���y��𐁂��̂͒[���猩���肸���Ɠ�����̂��Ə��߂Ēm�����B����̎Q���҂͒��w����Ⴂ�l���肾���A�Ƃ�ł��Ȃ����ɖ�������ł��܂����B�ł��������ɂ͈����Ȃ��B�������o���Ɗo������߂��B
 |
 |
| �����ł̃��n�[�T�����i |
�����̂s�V���c�ŏo�Ԃ�҂� |
���\�Ƃ���o��c�̂̒��ʼn�X���R���t��`�[�����������ł͍ł��n���������B���̒c�͈̂ߑ�����哹��E������܂ŁA�F�Ƃ����f�U�C���Ƃ����Ƃɂ����h�肾�B�Ⴂ�����̘I�o�x�����[�ł͂Ȃ��B���̓�����͖ڗ����ƁA�ϋq������邱�Ƃ����`�Ȃ̂��B
���āA���悢��o�Ԃł���B�Ƃ��낪�X�s�[�J�[���痬���A�i�E���X�̐��⑼�`�[���̑剹�ʂ̉��y�ɂ���������ăX�^�[�g�̓J�̍��}���������Ȃ��B���܂��Ɍ�ʐ����̂��܂�肳��̓J�����ꍞ��ł���B�����Ȃ�Ύ��o�ɗ��邵���Ȃ��B���͂̒��Ԃ������o�����̂��@���čs�i���J�n�����B�������Ė�P�j���̓��̂���N�����l�b�g�𐁂��Ȃ���A����ɃT���o�̃��Y���ɍ��킹�ăX�e�b�v�݂Ȃ���p���[�h�����̂����A�S�[���ɂ��ǂ蒅�������ɂ͑S�g���т������ő����₦�₦�̏�Ԃ������B�G�[���[�ƃT���o�̊W�͂��Ȃ艓�����Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B�r���R�����̍̓_�����������������A�炪�����w����������C���̔N���G�[���[���������_�̑ΏۂƂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ�ɖ]�ނ���ł���B
���̓��̗[���ɍs��ꂽ�z���c�̗��K�ł͖��炩�ɏW���͂������Ă��ĒP���ȃ~�X��A�����Ă��܂����B���߂�Ȃ����B |
| 8��23���i���j�c�������� |
���C�i�[�E�~�����[�E���@���E���N���Ƃ������O�����߂ĕ������̂͐������O�A�z���c�̉���Ă̏��ʂj�������炾�����B�u���݃h�C�c�N���ň�ԗǂ������Ă�̂͒N���낤�H�v�Ƃ�����b�����킵�Ă��������B��x�ł͕������Ȃ����O�̂��̑t�҂͖��N�Ăɒ��쌧�ѓc�s�ŊJ����鉹�y�Ղɗ��Ă���Ƃ����B
�����C���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ݂�Ɓu�A�t�B�j�X�Ẳ��y�Ձv�Ƃ����z�[���y�[�W�Ɏ��̊�ʐ^�ƂƂ��ɗ������ڂ��Ă����B�n�m�[�t�@�[���܂�A�g�E�_�C���c�@�[�Ɏt���A�U�[���u�����b�P����������ȁA�}���n�C�����勳���Ƃ���B�_�C���c�@�[�̒�q�Ȃ�U�r�[�l�E�}�C���[�Ɠ��傾�B�ѓc�Ȃ�n���I�ɂ��߂��B����͐���Ƃ������ɍs���˂Ȃ�܂��B
�Ƃ����킯�ŁA�������P���ł͂����������ۂɎ����̎��Ń��N�����̉��t���A���b�X���u���A�܂��e������b���邱�Ƃ��ł����B���̉��͊m���ɍ��܂Œ��������Ńx�X�g�ƌ����鉹�������B�_�炩����ݍ��ނ悤�ȋ����ł���Ȃ��特�̐c�͂�������Ƃ���B�_�C�i�~�b�N�����W�͍L���A�s�A�j�V���ł��m�C�Y�͊F���A�t�H���e�V���ł������Ĕj�]���Ȃ��B
����͉��Ƃ��Ă����̉��̔閧���o�������ƁA���̂P���̃X�P�W���[�����I������������v����Ęb���|�����B�P�X�O�����͂��낤���Ƃ������g�����m�I�ŗD�����ڂ����Ă���B�������G�[���[�𐁂��Ă���Ǝ��ȏЉ��Ƒ�w�����A�t�Ɏ���U�߂ɂ������B���{�ŃG�[���[�𐁂��Ă���v���͉��l����H�z���c�̉���͉��l�H�h�C�c�l������H�N�ł������́H���X�B��������������Ǝ��₵���B���[�h�́H�}�E�X�s�[�X�́H�y�탁�[�J�[�́H���̓����́u���[�h�̓��@���h�����̃z���C�g�}�X�^�[�i�T�O���ɂP���ʂ����ǂ��̂��Ȃ����ǁj�v�u�}�E�X�s�[�X�Ɗy��̓N�����^�[���[�i�j�q�n�m�s�g�`�k�d�q�j�v�Ƃ̂��ƁB���̏������[�J�[�̊y��͉��ǂ̃g�[���z�[�����^������Ȃǂ��ăm�C�Y��啝�ɒጸ���������ŁA�ڂ̑O�ł������Ɣ����K�𐁂��Ă��ꂽ���A�Ȃ�قǑS���ƌ����ėǂ��قǕ��艹�����Ȃ��B�d�グ���u���c�@�[���ɗD��Ă���B
���̉����̑f���炵�����^����Ɓu�����܂ŗ���̂ɒ������Ɓilong
time�j�|��������A�A�A�v�Ɩ��ɂ���݂茾�����B
 |
 |
 |
 |
| ���y�Ղ̃��C�����ѓc������� |
�l�̃N���𐁂����N���搶 |
���ɏ���ăE�F�[�o�[�̃R���`�F���g�� |
�z�e�����r�[�Ő[��܂ő��������y���t�� |
���āA�����ŐS�Ɋ����Ă����������s�Ɉڂ����B�uCould
you please play my clarinet?�v�uOh,
sure.�v�Ƃ����킯�ŁA�}���ʼn䂪�����g�ݗ��Ď��̑O�ɍ����o�����B�O���Ɏ����Ƃ��Ă̓x�X�g�̃Z�b�e�B���O���{���Ă������̂��B�}�b�s�͂f�R�q�C���[�h�̓t�H���G�b�^�c�^�C�v�̂R�Ԃł���B���N���搶�u�ف[�A�x�`�l�`�g�`���ˁv�Ȃǂƌ����Ȃ���b��������������J�����B�u����A�Ȃ��Ȃ��ǂ�����Ȃ����B�����_�炩���悭�L���邵�B�����A���u�V���A���������肵�Ă����Ȃ��Ɖ����������肪���ɂȂ邩��C��t���Ăˁv�B���[�h�̓t�H���G�b�^���Ɠ`����Ɓu�t�H���G�b�^���I���[�R�t�i�����j�́B�l�������Ԏg���Ă���v�Ƃ̂��ƁB�������A���̕����͂����傫������Ă��Ȃ��炵���B�t�H���G�b�^���}�C�i�[�ȍە��ł͂Ȃ��悤���B���ꂳ��������ΖړI�͒B�����悤�Ȃ��́B�͂��ѓc�܂ŗ����b�オ�������B
���̑��G�k����B�h�C�c�Ńx�[���������Ă�Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��B�h�C�c�Ńx�[���𐁂��Ă�v���͎������m�����V���c�b�g�K���g�̂P�l���܂߂ĂT�l�ʁB���K�`���[�̓C�V�����̃V���o�[�����p���Ă�B�J�b�p�[�i���j�̕��������ƈ������ǂقƂ�Nj@�\�͕ς��Ȃ��B�����O�C�V�����ɍs�������ǃ~�X�^�[�E�C�V�����͗��炾�����B���H�z���c���h���X�f���Łu���e�v�����t������āH����������Ȃ����A�撣���I���N�P2���ɃU�[���u�����b�P���������̈���Ƃ��čė������A�~�X�^�[�E�r���ƃX�N���o�`�F�t�X�L�[�̎w���Ńx�[�g�[���F���̌����Ȃ����t�����A���X�B
���N�����̉����I�P�̒��łǂ̂悤�ɒ�������̂��낤�H����m���߂ɍs���������̂��B |
| 8��11���i���j��������ċx�� |
����X���Q���i�y�j�ɊJ�Â����É��t�B���n�[���j�[�nj��y�c�Ɖ��|��s���I�[�P�X�g���Ƃ̃W���C���g�E�R���T�[�g�̂��m�点�ł��B
�Ãt�B���͗��N�n���R�O���N���}����É����A�}�I�P�E�̖���ŐÉ��s�𒆐S�Ɋ����ȉ��t�������s���Ă��܂��B�c�����P�O�O���߂�����悤�ŁA�n���킸���S�N�̂�����܂�Ƃ����|�I�P�Ƃ́u�i�v���Ⴂ�܂��B�Ȃ����j���K�͂��������_���قȂ�Q�̃A�}�I�P���|��ŋ������邱�ƂɂȂ����̂��H�E�E�E�悭������܂���B���A�ꉞ�u�|��s�����L�O���Ɓv�Ɩ��ł��Ă���悤�ɁA�s���V�|��s���̈ӌ����傫���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�Ãt�B�����͂ǂ��v���Ă��邩�m��܂��A���c�ɂƂ��đ���ɕs���͂���܂���B�c���͉�R�R�ӎ���R�₵�Ă��܂����A���́A���͂≉�t�Z�p�Œ�����肵�Ēp�����������Ȃ��Ƃ����̂��{���ł��B���āA���t�Ȗڂł����A����́u�y�[���M�����g�S�ȁv���t���A�Ƃ����ȋ��𓊂��Ă��܂����B�������ꕔ�̓x�e�����L�����D�A��_����q����ł��i���͂悭�m��Ȃ��j�B����͉�X�ɂ͖Â����D�̏P���ɕC�G���܂��B�}�������c�͐��ʌ��j�͕s���ƌ��āu�V�ˎq���l�{�{�����v�Ƃ����閧�����p�ӂ��܂����B�l���ł͕����Ă��l�Z�ŏ����I�Ƃ������ł��B�V�ˎq���̈�l�͊|�I�P�ɂ͂�����݂̒����t�Ԃ���i���ݓ����|��t�����Z�P�N���j�ŁA�����f���X�]�[���̃��@�C�I�������t�ȑ�P�y�͂��A������l�͐É����w�����y�R���N�[���ŗD�������|��o�g�̒��w�R�N���A����b�O�N�ŁA����Z�I�ȃT���T�[�e�̃J���������z�Ȃ����t���܂��B
�����Ō����̂��������܂����ł����A���݊|�I�P�̊NJy��Z�N�V�����ɂ͖��肪�����Ă���̂Łu�{�����v�����Ȃ蕷�����ł��B��t���[�Y�ň��������g�����{�[���E�\���́A����S�l�̃����o�[���S�c���̑O�ʼn��t���A�������őI��܂����B�N�����l�b�g�͂Ƃ����ƁA�Ⴍ�ď�肢��l�̑��_�Ƀ\����C���A�l�͉��X�ƃ��A���A�t�@���o�Ă��Ȃ��o�X�N���ɉ���ă��N�����悤�Ƃ��Ă����̂ł����A�}篈�l���{�Ԃɏo���Ȃ��Ȃ�l���a��ǂ̃\���𐁂��H�ڂɂȂ�܂����B�G�[���[�ɂ��{�����Ƃ����̂����{�ł͂߂����ɒ����Ȃ��M�d�ȋL�^�ɂȂ邩���m��܂���i�B
���̃R���T�[�g�̍Ō�ɂ͂Q�̃I�P�������Łu�Е����X�v�Ȃǂ����t����\��ł����A���̋����X�e�[�W�ɑS������̂��A�����ɂȂ��Ă݂Ȃ���ΒN�ɂ�������܂���B��������������L�́u���܂������_�v�Ƃ�����Ȃ̂ł��傤�B
�Ȃ��A���x�̂P�S���i���j�Ƀ\�������ă����R���ƃJ�������̌��J���K���s���܂��B�|��ߕӂɂ��Z�܂��̕��i���Ȃ����j�͂P�X�F�O�O�`�Q�P�F�O�O�ɐ��U�w�K�Z���^�[��S��c���ɂ��z�����������B�����̋����A�\���X�g���搶�̃T�C���t���B���������A���̃X�������O�ȁH�W���C���g�R���T�[�g�̃`�P�b�g�i�O����P�C�T�O�O�~�j����]�̕��̓��[�������������B |
| 8��8���i�j�䕗���� |
 |
| �P�O���A�h���X�f���ł�����܂��傤�I |
�����A���܂��܂m�g�j�a�r�Ƀ`�����l�������킹����A��N�̑��É��y�Ղ̃R���T�[�g����A�l�����x�����t�������Ƃ�����x�[�g�[���F���́u���d�t�ȁv������Ă����B���t�҂͉��y�Ղ̍u�t�w�Ȃ̂��낤�A���ȃA���T���u���̊����x�͂��܂����B�N�����l�b�g�͈꒮���ăx�[�����Ǝv�����̂����A���Ɖ�ʂɎʂ����̂̓G�[���[�ł͂Ȃ����B�t�҂̊�̓s�G�[���E�u�[���[�Y�Ɏ��ĉ₩�ɂ͎v���o���Ȃ��������A�͂��Ǝv�����������B�U�r�[�l�E�}�C���[�̂��Z����A���H���t�K���O�E�}�C���[���B�������͌��݃h�C�c�N�����l�b�g����̉����ł���A�m���i�������{�l�Ɏ��o�͂Ȃ����낤���j�z���c�̉���ł�����B���N���Âɗ��Ă����Ȃ�Ēm��Ȃ������B�����ƕ������ĉ�ʂɊ���t���Ċς��̂����A�ꌩ�N�����|���̃G���[�g�̂悤�Ɍ�����y��͈�̂ǂ��̂��낤�B�����O���������炩�^�������ɒ��������邾�����H���K�`���[�͏���߂̋������i�C�V���������j�B
�̐S�̉��F�́A���邢�Ƃ������A�N���A�Ƃ������A�����đ����͋��������ł͂Ȃ��B���Ɋɂ₩�ȃ��B�u���[�g���������肵�Č��\���ڂ̃��[�h�Ń��N�ɐ����Ă���悤�Ɏv�����B�t�@�S�b�g��z�����ƃ��j�]���Ő������ɂ͋����ɗ֊s��^����悤�ŏ_�炩���������̂����A��Q�y�͂̂悤�Ȃǃ\���ƂȂ�Ƃ����������݂≷�����������Ă������B�A���u�V���A��y��̍\�����̓U�r�[�l�ɂ�������A�Ƃ����̂����Z����ɂ͎���Ȍ����������A�قƂ�Ǔ����Ȃ����Ă���v�X�̂b�c���ƁA�����̓_�łق�̋͂����T�r�[�l������s���Ă��āA�V�˂Ɏ��Z�Ƃ����̂���ς��ȁ[�A�Ƃ����C�ɂȂ��Ă���B |
| 8��6���i���j�Ђ����珋�� |
�Z�b�g�A�b�v���TEST�B�E�E�E����ꉽ�Ƃ������悤���B
 |
| �ߏ��̉čՂ��ꂩ�畷�����Ă����a���ۂ̋��� |
�܂��p�\�R���̒��q�������Ȃ����B�P�����قǑO����₽��ƃG���[���b�Z�[�W���o��悤�ɂȂ��āA�ŋ߂ł͋N���ɂQ�O����v���A���̌�̓�������X���[�B�E�B���X��X�p�C�E�F�A�̃`�F�b�N�����Ă�����ُ�͂Ȃ��B�p�\�R���V���b�v�Ⓦ�ł̃t���[�E�_�C�����ɑ��k�������ʁA�t���̃��J�o���[�EDVD��OS���ăZ�b�g�A�b�v���邱�Ƃɂ����B����Œ���Ȃ���n�[�h�f�B�X�N�̋@�B�I�����Ȃ̂Ń��[�J�[�֏C���ɏo������Ȃ����A���̏ꍇ�͖�P������v���A�������R�C�S���͎���邾�낤�Ƃ̂��ƁB
�Z�b�g�A�b�v�͂���łR�x�ڂ����A�f�[�^�[�̃o�b�N�A�b�v��A�v���P�[�V�����E�\�t�g�̍ăC���X�g�[�����ʓ|���̏�Ȃ��B���̍ۂ��̑傫���āi�P�T�����j�d���āi�RKg)�g���u�������̃p�\�R������߂āA���^�E�y�ʂ̃��o�C���E�p�\�R���ɂ��悤���A���łɗ���Ȃ��É��̃v���o�C�_�[�����ɕς��悤���ȂǂƎv�����点�Ă�����ɂ��ǂ�ǂ�Ǐ����B���̂܂܂ł͒~�ς����f�[�^�[�����ł����˂Ȃ��̂ŘA�x���Ԃ��ĂƂ��Ƃ����z�������s�����B�ǂ����Z�b�g�A�b�v�͐��������悤�ŁA�܂�Ō��Ⴆ��悤�ɃT�N�T�N�Ɠ����悤�ɂȂ����B�o�b�N�A�b�v�p�̂b�c�|�q�i�R�O�~�j�ȊO��K���|����Ȃ��������Ƃ͍K���ł���B�ߋ��̃��[����A�h���X��Z���^�◚���͑S�ď����Ă��܂����̂ł܂�Ő��܂�ς�����悤�Ɋ�������A�Ƃ����̂͂₹�䖝�B |
| 7��22���i�y�j�Y�ꂽ |
MINI�l���̃Z�[���X��Fj�N����d�b������ADM�����Ă���܂������H�����B���������Έ�T�ԂقǑO�ɗ��Ă������A�ǂ����W����̈ē����낤�ƁA���g���ǂ܂��Ɏ̂ĂĂ��܂����B�����`����ƁA�ǂ��b�����邩�琥�X���ė~�����ƌ����B�����ւ���C�͑S�������������A�ŋ߂�MINI�͂ǂ��ς���Ă���̂��������������̂ŋv���U��ɓX��K�˂��B
 |
 |
 |
| �������S�̓I�ɔh��ɂȂ����� |
��[�̃����v�̓E�b�V���[�t�x�������Ƃ� |
���F�������Ȃ�ƕ����čQ�ĂĔ�����MINI�J�[ |
�ǂ��b�Ƃ����͉̂����̋��z�ŁAFj�N�̘b�ɂ��ƕ��ʏ��߂Ă̎Ԍ��O�A�܂�R�N�����̉���艿�i�͍w�����z�̂S���Ƃ����̂����ꂾ���AMINI�̏ꍇ�͒��X������l�����Ȃ����MINI�̒��Â��o��̂�҂��Ă���l���吨����̂ŁA�T�`�U���ʼn����Ƃ̂��ƁB�l�͈̂�Ԉ���MINI
ONE�̂������}�j���A�������A����ł��P�P�O���Ƃ���������z���B���[�ށA�m���Ɉ����Ȃ��b�ł͂���B�����S�����ꂩ���čŐV��MINI���e�ׂɊώ@�����̂����ǂ����]�芴�S���Ȃ��B���͐��\�͕ς�炸�A�t�����g�O�����Ƀ��b�L�ނ������A�w�b�h�����v�̃f�U�C�����q�����ۂ��Ȃ����B�A�܂����v�����̂̓T�C�h�o�C�U�[�̒lj������������BMINI��BMW�̓����̖ژ_�����w���w�̔N������A��N�w�ɕs�l�C�������̂Ńf�U�C������Ҍ����ɕς��Ă���Ƃ����L����ǂL�������邪�A�����̐헪�ύX�͋p���Ĉ��I��炸�ɂȂ肩�˂Ȃ��B�����������̃N���}�̃I���V�����͑�l�ɂ�������Ȃ��̂��BFj�N�ɗ����Ȋ��z��`���A��������MINI�ɏ�邱�Ƃ�`����ƁA�u��͂肻����Ǝv���Ă܂����B���͗��N���f�����烊�L�b�h�E�C�G���[�������Ȃ��ł��v�ƌ����B���̍Ō�̈ꌾ�łP�O�N�P�O��Km�ւ̌��S�͌ł܂����B |
| 7��15���i�y�j�^�Ă̂悤 |
 |
| �l���s�y�˒��P�U�P�W�|�P�Q�O���x���O�T�R�|�S�V�R�|�O�W�S�W |
������A�ˑR��Ђ̌�yM���N����t�������āA��Ђ����߂ċi���X���n�߂��ƒm�炳�ꂽ���ɂ͐����������B������ސE��������ɂ���Ƃ͂����A���ǂ��i���X�Ő��v�����Ă���̂��낤���H�������n�}������ƕl���s�̏Z��X�̐^���B���M���^�œX��K�˂��̂��P�N�O�������B����ƌ������ڈ���Ȃ��V���Z��n��MINI�ŎU�X�����Ȃ��甭���������̓X�͂܂��ɐV�z�Z��̂��̂ŁA���̏Z��Ƃ̈Ⴂ�͕ǂɁunoncurante�v�i�m���N�����e���Ɍ�Łg�C�y�ȁh�Ƃ����Ӗ��炵���j�Ƃ����X�����f���Ă��邭�炢�������B�X�ɓ���Ɖ����̊Ԃɂ�����ѕE�₵��Ms�N�Ɖ������҂��Ă��ꂽ�B���͓�l���������킹���̂͂Q�O�N�O�̖l�Ȃ̂��B
�ЂƂ�����̘b�ɘb���e���Ms�N�����J�ɟ���Ă��ꂽ�R�[�q�[��Ղ��ƁA���ꂪ���ɔ����������B���ł��S�������R�[�q�[�̐搶�ɒ�q��������肵�Ē��X�Ƀm�E�n�E��`�����Ă�������炵���B�����@���A�i���O���ƍ����ȃf�W�^�������w�����A�������ʂ����������Ĕ̔�������Ƃ̂��Ƃ������B������S�z�������̂́A���̔���������t���ẴR�[�q�[���������̂R�T�O�~���������ƁB
���̓�l�͂��̌��肭�s���Ă��邾�낤���H���̂P�N�ԁA�����S�̋��ŋC�|���肾�����B�����A����ĂіK��Ă݂Ăǂ���炻��͞X�J�ɏI������悤�łق��Ƃ����B�X�͂ƂĂ��ɐ����Ă���悤�������B�l���X�ɓ��������̓J�E���^�[�Ɉ�Ȃ��Ă��邾�����������A�q���A��܂��q�������Ă���ƌ�������B�u���A���܂ŌŒ�q�������܂�����v��Ms�N�����ށB�u�T�Ɉ��̋x�݂����o���ŖZ�������āA�A�v�Ǝ��胉���`�̃g���e�B�[�����o���Ȃ��牜��������Ă���B
 |
 |
| Ms�N���E�̉~���^�h���b�p�[�Ɛ�p�h�� |
�J�����V���T�J���Ăǂ��̓��H |
����͔��������R�[�q�[�̟������Ms�N�ɂ�������Ƌ����Ă�������B���͋Ɩ��p�̃t�B���^�[���h���B���͕��������Ă���X�O���ɉ�����B�����h�����g�����ׂ͍����҂��B�h���b�p�[���h���͈�_���o�̉~���^���g���B�͂��߂͓����ׂ����ՂȂ��R�[�q�[�̕��ɐ��炷�B�������炵�Ă��瓯�S�~�`���Ȃ����C�ɒ����A�ȂǂȂǁB�u�ł�����ς薡�̌��ߎ�͓��̎��������̎d���ł���v�ƈꌾ�B�v������錍������ē���������ɉ~���^�h���b�p�[�ƁA���̓X�̈ꉟ���Ƃ����u�J�����V���T�J�v�Ƃ������킹�Ă�������B�������Ă��ꂽ��l�Ɏ��U��Ȃ���A�v�w�ŗ͂����킹�Ė�����������Ă����ȂƎv�����B |
| 7���W���i�y�j��������� |
 |
| �ό��q�œ��키����̑P���� |
�N�����l�b�g�t�F�X�e�B�o��in����Ɂu�z���c�̉�v�̈���Ƃ��ĎQ�������̂ŁA���߂Ē���s��K�ꂽ�B���ƂȂ����{�s�̕����L���ȋC�����邪�A�����������Ƃ����������ݒn�ł���A�u�l�����S�O���l�ŏ��{���P�O���������v�ƒn���^�N�V�[�̉^�����͑������Ă����B���n�[�T���̑O�Ɏ��Ԃ��������̂Ŋό������ł���P�����������ɍs�����B�m��Ȃ��X���U��͎̂��ɕ��������Ɗy�����B
����Ȑm���������e�ɗ����͂�����R���������Ɠ��X����{�����p���������B�K�i���オ��Ə����ȍ����̎���ɐl�����肪���Ă��āA�F������ɂ��̑��ɐG���Ă���B�悭����Ƃ��̖ؒ��̑��̊��葫�͂��ɖ��茸���Ă���B���ł������̊����Ă��鏊��G���Ă���u�т鑸�ҁv�ƌĂ�邻�̑��̓�������G��ƕa������ƌ����`�����Ă��邻�����B�c�̃c�A�[�̃K�C�h���A�u�������ԈႦ��Ɖv�X�����Ȃ�܂���v�Ȃǂƌ����ď킹�Ă���B�l���]���^���M���O�������Ȃ�悤�ɐ�ɐG�낤���Ǝv�������A�т邳�̂���ڂ��ł͂��������Ȃ������B
���āA�M�B�ƌ��������ł���B�ʂɋ����̖��ɂ��邳����ł͂Ȃ����A�܊p�M�B�ɗ����̂��A�ǂ������������ȓX�͖������Ƒ{�����Ƃ���A��ł��̎��������Ă���Â߂������������������ē������B�u��ہv�Ƃ��������̂��̓X�͘V�܂炵���X�\���Ȃ̂ɈӊO�ɂ��l�i�������A����ԍ����V�Ղ�X�Ȃ��ł��P�C�R�O�O�~�ł���B��ł��˂ɂ͓K�x�ȃR�V������A����Z���ڂŃ_�V�������A�V�Ղ���g�����Ăő喞�������B�����A�^�Ă̂悤�ɏ����������̓��A��Ԕ������������̂͋߂��̊Ö�������ŐH�ׂ��N���[������݂����������B
|
| 7��5���i���j�J�A�T������ |
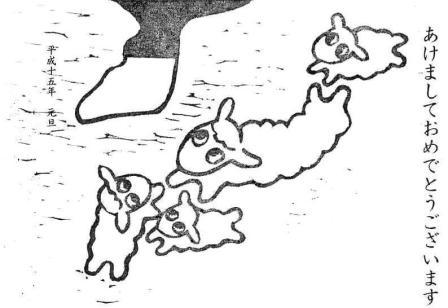 |
| �����P�T�N�̔N���̔ʼn�B�r�̂悤�ɋ�������{�� |
�R�N�O�̗a�����I���I�H�k���N���u�e�|�h���v���́u�m�h���v���̂𐏕��h��ɑł��グ���B�ԉΑ��ɂ͏��������悤�ȋC�����邪�A�����y�ȓ��{���{�ɂ͗ǂ��C�t����ɂȂ����낤�B
�f�v���ŎU�X�k���N����o�J�ɂ���Ă��o�ϐ��قɓ��ݐ�Ȃ������㍘���{���A�~�T�C�����V�������˂���Ă���Ɩڂ��o�߁A�Q�ĂČo�ϐ��ق�����Ƃ����̂��������Ȃ�����ɏ�Ȃ��b���B������v���X���[�@�ł͂��Ⴂ�ł鎞�łȂ��ėǂ������ˁB�^�����͂̓����B����̎����ň�ԓ��������͈̂������[��������Ȃ����낤���B���ꂾ����Ńv���[���X���オ��Ύ����ԈႢ�Ȃ��H
���݂Ɂu�e�|�h���v���u�m�h���v�����̑��݂��m�F���ꂽ�k���N�̒n���ŁA�A�����J������ɖ����������̂��������B���̃A�����J���C���N�Ŏ��s���Ă��邩��ȒP�ɂ͎���o���Ȃ��B�����ڂ̃u�b�V���ƈ��ފԋ߂ȏ��ǂ̂悤�ȑΉ�����u���邩�H�������̐��r�łւ̍��ۓI�u�l�ߏ����v�̓T�b�J�[�̃��[���h�E�J�b�v�Ȃ�肸���Ƌ����[���B |
| 6��21���i���j�������� |
���N�̓��[�c�@���g���a�Q�T�O���N�ɓ�����̂ŁA���������̃e���r�ǂŃ��[�c�@���g�̓��Ԃ�g��ł���B�l�������y���݂ɂ��Ă���̂�NHKBS�n�C�r�W�����ŕ������Ă��邻�̖����u�������[�c�@���g�v�B���V�F�R�O����Ȃ̂ŏo�̎x�x�����Ȃ��猩��̂ɂ��傤�Ǘǂ��B���[�c�@���g�̎q���̍��̋Ȃ���N�㏇�ɑ�\����A�֘A����l���⌚���╗�i���̉f���ƂƂ��ɗ����Ă����̂ŕ��ɂ��Ȃ�B
�����A��X�W��ڂ̍�i�̓E�B�[���̍c�郈�[�[�t�����D�����n�����j�[���W�[�N�̑�\��u�O�����p���e�B�[�^�i�P�R�NJy��̂��߂̃Z���i�[�h�j�v�������B����ԑg�̖`���ɍ�i�ɑ���L���l�̉���Ƃ������v������݂����ȃC���^�r���[������B�����͔o�D�̍]��^������������͖��������Ȃ��B
���āA�Љ��鉹�y�����O�̃��@�C�I������s�A�m�Ȃ�ӂ�ӂ�������Ȃ��璮���Ă���Ηǂ��̂����A���ƃN�����l�b�g�����閼�ȂƂȂ�Ɣԑg�̌�������R�������Ȃ��Ă���B
 |
| �������ĕ���������P�T���̂��E�ߔԑg |
�܂��A���y���P�R�ǂȂ̂ɉf���͂Ȃ����s�A�m�Ɩ؊ǎl�d�t�Ȃ̂��B�������o�Z�b�g�z������R���g���t�@�S�b�g�Ȃlje���`�������B�܂��A����͓K���ȉf���f�ނ�������Ȃ������Ƃ������Ƃŋ����Ƃ��悤�B�z�����͂����ƃE�B���i�E�z���������A�I�[�{�G���E�B���i�E�I�[�{�G�����A�N�����l�b�g�i�����j���E�B�[���E�A�J�f�~�[���̃n���}�[�V���~�b�g�𐁂��Ă���B�悭���{���Ă����ƌ����邩������Ȃ��B
�Ƃ��낪�ABGM�̉��t�c�̂̃e���b�v���o�ċ����߂��Ă��܂����B�u�x�������t�B���NJy���t�c�v�B�Ȃ��u�E�B�[���t�B���NJy���t�c�v��I�Ȃ������̂��H���������̂��������������Łu�旳�_�˂������v�Ƃ͂��̂��Ƃ��A�Ƃ����悤�ȈӒn���Ȑ��ɂ߂����撣���đ����Ăق����B |
| 6��4���i���j���� |
 |
| ���t��̗l�q��`����É��V���̋L���B�V�O����Ėl����Ȃ��� |
����̊|�I�P��S�������t��͗ǂ����t������B�Z�r���A�̏��Ȃł͂܂����������������Ȃ���������ǁA���[�c�@���g�ƃ`���C�R�ł͊|�I�P�̎��Ă�͂��o���ꂽ�Ɗ������B���Ƀ��C���̃`���C�R�̂T�Ԃ͏o�����̃N���̃��j�]���������ŁA���ْ̋���������ɑ����e�Z�N�V�����̉��t���x���������グ��̂ɍv�������B�l�͍~��ԁi�P�A�V�j�����������̎Ⴂ��l�̓������ւ�Ɏv���B
�������q�l�̃A���P�[�g��S���ǂB��͂�`���C�T�̐���オ����^���鐺�������������ǁA���[�c�@���g��e�������c�N�̃s�A�m�ɖ����ꂽ�Ƃ������z��������ꂽ�B�ނ̎הO�̂Ȃ������ȉ������[�c�@���g�̐����y�ɂƂĂ��}�b�`���Ă������炾�B�n���̎s���I�P�Ƃ̋����������ł��ނ̌o���⎩�M�Ɍq�����Ă����Ί������B�u�Ȗډ����������₷���Ă悩�����v�Ə����Ă��ꂽ�l���P�l�����B����Ȉꌾ�Ŋ�Ԑl���ǂ����ɂ���̂�����A�ǂ�Ȃ��Ƃł��J�߂Ă����܂��傤�ˁB
���āA���ӂ͕l���̃A�N�g��z�[���ō�搶�����}�n���t�y�c���w�������B�Q���Ԕ��ɋy�ԑ�R���T�[�g�ŁA�Ϗ���i�i�܂���{�����j���R�Ȃ�����A�Ō�̓o�[���X�^�C���́u�L�����f�B�[�h�v���I�y���`���ʼn��t�����̂����A���ꂪ�܂������I�ɑf���炵���A����̊��т��Ă����B�O���|��ŃN���V�b�N�̖{�Ԃ�U��A�����l���Ő��t�y�̖{�Ԃ�U��B�Ȃ͍��v�P�O�Ȃɂ��Ȃ�B�����Ƒ��ɂ���R�Ȃ�����Ă���ɈႢ�Ȃ��̂����A��̓��̒��͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤�H
����ȂɖZ�����X�P�W���[���ɂ�������炸��s����ڂ����A���������w���ɗ��ĉ������搶�ɑ��A��������ӂ̋C������Y�ꂸ�ɗǂ����t�����ĕ������̂��B |
| 5��30���i�j�����͐l�吙 |
 |
�T���g���[�z�[���Ȃ�ĉ��N�Ԃ肾�낤
�������܂����t�@���t�@�[���͎~�߂Ă��� |
�M�����^�[��K�˂���N���X�g�t�ɉ�����B�o���x���N�����y�c�̎�ȑt�҂�Viotto�̃}�E�X�s�[�XG3�i�Q�[�E�h���C�j�̊J�����͎҂ł���M�����^�[�E�t�H���X�g�}�C���[���Ƃ́A�ǂ�Ȑl���łǂ�ȉ��łǂ�ȉ��t������̂��낤�H���̍��܂鋻���Ɗ��҂���������A��Ђ̒n�k�h�ЌP���������ۂ����āA���������ƃT���g���[�E�z�[���܂ŏo�|�����B���N�n���U�O���N���}����Ƃ����o���x���N�����y�c�͍��P�P�x�ڂ̗����ŁA���̖�̉��t�����傤�ǒʎZ�P�O�O��ڂ̋L�O���ׂ����{�����������������B�������͂P�X�U�W�N�A�������̃��[�t�E�J�C���x���g�̎w���Łu�p�Y�v�����t�����B�����e���r�ł��̉��t�������ǁA��S�y�͂̃N���̂�����肵����s�^�̃\���i�h�E���E�~�E�t�@�E�\�E���E��V�j���@���ɂ��h�C�c�ǂ炵�������ŗ͋������F�������ƋL�����Ă���B����̉��t��v���O�����̓N�������̗͗ʂ�m��ɂ͑ł��Ă��́u�������v�Ɓu�x�g�V�v��I�B���̃I�P���̂̎��͂͂ƌ����ƁA�ܘ_���Ȃ�̍������x���ł͂���̂����A������ƍr���ۂ��Ƃ������������Ƃ�Ă��Ȃ��Ƃ������A�x�������t�B���̂悤�ɒ��ꗬ�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B�^����ɃN�r�ɂ��ׂ��̓g�����y�b�g�ŁA�ύ\�킸�����U�炷��ɁA�A�C���U�b�c�Ŕ�яo������A�������Ƃ�ł��Ȃ��ジ�����肵�đS�̂̈�ۂ�啪���˂Ă����B�܂��A���g�Ŕ��l�̃I�[�{�G��͊m���ɉ����ǂ���肢�̂����A�}�C�y�[�X�ȃe���|�Ŕ��t�Ƃ��ꂽ��A�y���ɂȂ��Ǝ��́i����ȁH�j�A�[�e�B�L�����[�V�����Ő������肵�Ă���B�܁A�S�Ă͎�Ȏw���҂ł���W���i�T���E�m�b�g�̓����͂̎コ�ɋN�����Ă���̂����A�ގ��g���̃I�P�ɂ����Ɨ��܂낤�Ƃ����C�͂��炳��Ȃ��̂��낤�B���āA�̐S�̃N�������A�P�����̐Ȃɍ����Ă����͈̂ӊO�ɂ���ҁB�u�������v�Q�y�͂̒����\���͂Q�u���X�Ŗ���ɐ��������̂́A����ߖ����߂��A���C�̃N���b�V�F���h�������Ȃ��B�u�x�g�V�v�̂Q�y�͂ł��S�̂̋�����~�������ē˂������Ă���͋���������Ȃ��B�u���������ȁ[�A���F�͊m���ɏ_�炩�����ǁA���ꂪ�ق�Ƃ�G�R�̉��H�����͔ނɗǂ����������������Ȃ������킸�ɋA�邩�A�A�A�v�ƏI����C�̂Ȃ���������Ă�����ɃA���R�[�����n�܂����B�Ƃ��낪���ꂪ���������I�G�l�X�R�̃��[�}�j�A�����Ȃ�����ɉߌ��ɂ����悤�Ȓ����}�̋ȁi��Ń��Q�e�B�́u���[�}�j�A���t�ȁv��S�y�͂Ɣ����j�ŁA�N�����l�b�g���劈��B�y��������̂����낵���悤�ȓ���ȃW�v�V�[���K�����̂����������Ő����܂���A���t��͎��͂̒c�����������ɏj������Ă���B�ނ͂�͂���҂ł͂Ȃ��悤���B
 |
| �����̋����H�N���X�g�t�N�̓i�C�X�K�C |
����ɗE�C�Ĕނ��y���ɖK�˂��B�y���͒c���ł������Ԃ��Ă��ĒN���M�����^�[�������S�����������Ȃ��B�b���ʘH�Ől���͂���̂�҂��Ă���v�����Ċy���ɔ�э��݁A�����ɂ����Ⴂ�c���Ɂu�M�����^�[�E�t�H���X�g�}�C���[����͂��܂��H�v�Ɛq�˂�ƁA���͔ނ��������̃N�����l�b�g�t�҂������̂��B�ׂ̒c�����u�ނ����͂����P�l�̎�ȑt�ҁA�N���X�g�t�E�~�����[���ł�����v�Ƌ����Ă��ꂽ�B����l�тĎ��ȏЉ��ƁA�N���X�g�t���́u�M�����^�[�͂�����̃v���O�����ɏo�Ă��邩�獡���͏o�Ԃ��Ȃ��B�����z�e���ŐQ�Ă��Ȃ����ȁH�v�Ƃ̂��ƁB�C�����ȃN���X�g�t���Ɉ��S���Ęb���e�B�u���{�̓x�[�������w�ǂȂ�H�z���c�̉���ĉ��l�ʂ���́HG3�̓������̓M�����^�[�̈Ӗ������Ēm���Ă��H�l�͌��x�������E�h�C�c�I�y���̃c�F���c�P�搶�̃}�E�X�s�[�X���g���Ă�B���������A���C�X�^�[�Ɠ�����B�h�C�c�ł͍��Ƃ��Ă��l�C�������A�A�A���X�B���N�P�O���Ƀh���X�f���ŊJ�Â����N�����l�b�g�E�V���|�W�E���ɎQ��������o���x���N�Ɉړ����A�Z�Q���P���̈ē��Ńo���x���N���������ɍs���\�肾�Ɠ`����Ƒ�w���ł���āu����A�o���x���N�ōĉ�悤�I�v�ƈ��肵�ĕʂꂽ�B���̎������M�����^�[���̉��������邾�낤���A�L�\�Ȏ��G�[���[�����ł���N���X�g�t�N�Ƃ̍ĉ���ʂ����邾�낤�B�h���X�f���E�c�A�[�̊y���݂��܂���������B |
| 5��24���i���j�₽��������� |
|
���͂U���R���A�܂藈�T�̓y�j���ɔ������|�I�P��S��艉�̃|�X�^�[�ł��B�����艉���ł��鐶�U�w�K�Z���^�[�z�[���ŗ��K���܂������A�ܗ����h��ł����蒆�X�̎d�オ��ł����B����Gm�̏o�Ԃ̓`���C�R�̂P�A�V�A���[�c�@���g�̃g�b�v�A���b�V�[�j�̂Qnd�ł��B�G�[���[�����̓��b�V�[�j�́u�Z�r���A�v���Â����Ă͂����܂���B�a��ǂŐ����ƁR�̃C�����ɂȂ�܂����A�Q�ӏ����郍�b�V�[�j�E�N���b�V�F���h�ł́u�p�e���gcis�L�C�v���劈�܂��B����Ȃɂ��̃L�C�̂��肪���݂���������Ȃ����Ȃ��ł��傤�B���[�c�@���g�̂o�R���́A�S�y�͂�ʂ��ăN�����Ƃ��Ă��g���������h�Ȃł����A�R�y�̖͂{�Ԃ̃e���|�i�܂葬���Ȃ�j����ł͐オ�ǂ����Ȃ��u�댯����v�����ӏ�������܂��B���̏ꍇ�͖����Ƀ^���M���O���Ēx�������u�X���[�Ő������Ⴆ�I�v�ƐS�Ɍ��߂Ă��܂��B�܂��A�ƂĂ��������Q�y�͖`���i�V���ߖځj�̃\���́A�G�[���[�ň�ԏo���ɂ�����̂b�́A���������i�s�A�m�j�Ŏn�܂�̂ŁA�����͑����ƂĂ��ْ����Ă��܂��o�Ȃ������ꂪ����܂��B�ł��A�o���ӎ��������ĉ��������������u�����ʂŐ������Ⴆ�I�v�ƐS�Ɍ��߂Ă��܂��B�Ȃ��A�v���O�������`���C�T�̋Ȗډ���������܂����B���߂��ɂ��Z�܂��̕��͐����ꉺ�����B |
| 5��21���i���j�v���U��̏��ėz�C |
 |
| ���肵���}�b�s�͑S���łP�P�� |
������߂ăx�[���ƃG�[���[�̎d�|�����v�����Ă݂Ă��̍����������Ȃ����Ƃ͈ӊO�Ȏ����������B�P�������鍷�ȂNJF���ŁA�قƂ�ǂ͂O�D�T�����ȉ��������̂��B�x�[���ł��h�C�c�ǂ炵�����F���o���l������A�G�[���[�𐁂��Ă��Ă��h�C�c�ǂ炵����ʉ���t�ł�l������B���ǂ͂��̐l�������Ă��鉹�F�̃C���[�W���y��Ƃ����C���^�[�t�F�[�X���o�ď����o�����̂ł͂Ȃ����낤���B�h�C�c�ǂ̉��F�C���[�W�����l�̓h�C�c�ǂƂ��̎d�|�����g�����������̃C���[�W�����������₷���ƌ����ɉ߂��Ȃ��̂��낤�B�����ŋߎc�O�Ɏv�����Ƃ́A�I�P��\�����Ă��h�C�c�ǂƃt�����X�ǂ̉��F�̍������Ē��ۗ����Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��B�l�╨�����R���Z���Ԃɍs����������ɂ����āA�������͎~�ނȂ�����Ȃ̂��낤���A�N���V�b�N���y�ɂ�����N�����l�b�g���t��S�̗ƂƂ���҂Ƃ��ẮA�h�r���b�V�[��x������Ȏ��ɃC���[�W�����ł��낤���F�ƁA�u���[���X��u���b�N�i�[���C���[�W�����ł��낤���F�Ƃ��������������ƍ��]�݂��A�����Ă��ꂱ��ƔY�ނ��ƂɂȂ�B�ǂ����͈���ƌ��������܂ł����A���������z�Ƃ��鉹�F�̃C���[�W�����߂ɓ��X���Ӑ[�����܂��������̂��B |
| 5��19���i���j�����~�J���� |
�|��s���a�@�̌��o�i���������j�O�Ȉオ�������f�f���ʂ́u�{�i�����j�ߏǁv�������B���̏u�ԁu����ς�ˁI�v�Ɩ��Ɋ������C�������N�������A���������ł���ꍇ�ł͂Ȃ��B�P�����قǑO�ɍ������̎��Â����Ă���H���̌��y��𐁂�����ɉE�̂������ɂ��Ȃ�n�߂��B���Ɋ|�I�P��z���c�̗��K�ŃN�����l�b�g�𐁂�����ɂ͏゠���Ɖ�����������Ċ��ݍ���Ȃ������ŁA�����Ɍ�����悤�Ƃ���ƉE�����̕t�����A�܂�E���̌��̕ӂ�Ɍ��ɂ�����B�܂��A�����J����x�ɂ܂�Ŗ����ꂽ�������̂悤�ɃK���K���A�S���S���Ɖ�������B
 |
�~�I�i�[���Ȃ��A�����Ȃ邩��
���ނȂ���ȁA�� |
�����Ő���A�z���c�̗��K��̂Q����Ŗk�C���x���j����t�ɑ��k����ƁA�u�����܂��������B�ق��Ƃ��Ƃǂ�ǂ��Ȃ邩�瑁���傫�ȕa�@�̌��o�O�ȂŐf�Ă�����������ǂ�������v�Ƌ������̂��B�|�I�P�ɂ���҂̗������ē������Ƃ������B����܂Łu���o�O�ȁv�Ȃ��啪�삪���邱�Ƃ���m��Ȃ������̂����A���o�O�Ȃ��Ă���Ȃɂ�邱�Ƃ���̂��ˁ[�B���̌��o�O�Ȉ�̓����g�Q���ʐ^�����Ȃ���l�̂�����͂�ʼn�������������肵�Ȃ��猾�����B�u�E�̂����̋ؓ����d�����Ă���̂ŃX���[�Y�ɓ����܂���ˁB���N�y��𐁂��Ă������ƂƊW������Ǝv���܂���B���ʂ̐����ł͂����̋ؓ����ْ������邱�ƂȂ���܂���B�ؓ����_�炩�������𑱂��Ĉ��߂Έꃖ���ʂŎ���܂���v�B�����Ȃ̂��A�܁A�m���ɂ��ȁ`�蒷���ԃN���𐁂��Ă�������ȁ[�B�N���}�Ō����P�O���j�������|���R�c�����B�������������͎̂R�X�����珈�����ꂽ��H��Ɉ��ݑ����Ă��邯�ǁA�ꃖ�����u�ؒo�ɍ܁H�H�H�v�݂����Ȃ��̂����ݑ����đ��v�Ȃ낤���H |
| 5��15���i���j����Ɛ��ꂽ |
�Ƃ��Ƃ����N�̒艉�v���O���������肵���B�e�p�[�g���[�_�[�Ȃǖ�Q�O���ō\�������u�I�Ȉψ���v�����M�����c�_�̖��ɏo�������_�́A�y�P�v���z���[�}�̎ӓ��Ձi�x�����I�[�Y�j�y���v���z�G�j�O�}�ϑt�ȁi�G���K�[�j�y���C���z�}�E���[���E���A�i�����F���j�ł���B�C���y�N�ł���l�͎i��E�i�s���ɓO�������A�����ɖژ_��ł����y�P�v���z�q�_�̌ߌ�y���v���z���E���@���X�y���C���z���v�\�f�B�[�E�C���E�u���[�͌����ɑS���������i�B�ł��܂��A����ȃv���O�����ʼn��t����J���A�}�I�P�Ȃ�Ď��Ƀ��j�[�N�����A�u���[�}�̎ӓ��Ձv���u�G�j�O�}�ϑt�ȁv���u�}�E���[���E���A�v���A�A�}�I�P����\�N�̊ԂɈ�x����������Ƃ��Ȃ��̂Ŋ��������肾�B���Ɂu�G�j�O�}�v�́u�A�_�[�W���i�j�����b�h�j�v���炢�����m��Ȃ��������A�����X�R�A���Ă݂��Ƃ���S���łP�S�Ȃ����邱�Ƃ����߂Ēm�����B�Ȃ̒�����Ґ��̋K�͂��炢���Ă������������C���v���ɂ���ׂ������m��Ȃ��B����ɂ��Ă��Ȃ��u�G�j�O�}�v������Ȃɕ[���W�߂��̂��H�����ɃG�j�O�}�i��j�ł���B
�N�ɐ������t�@������ĂȂ��A�}�`���A�ɂƂ��ē����Ȃ����x�����t����قǂ܂�Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B���̐��قǂ��閼�Ȃ̐��E���P�ł������̌����Ă݂������̂��B����ɉ��t�Ȗڂ������B�̈ӎu�Ŏ��R�Ɍ��߂���̂��A�}�`���A�̓������낤�B�펯�I�ɂ͖��d�Ƃ��v����o���g�[�N�́u�nj��y�̂��߂̋��t�ȁv�i�ʏ́u�I�P�R���v�j�𐄂����l�Ɠ�����̃��B�I���e�����ꂢ���B�u�����āA���̋@������炫���ƈꐶ�e�����ƂȂ����낤����A�A�A�v�B����A����悻�̋C�����B�l��Ɏc���ꂽ���Ԃ͂��������͂Ȃ�����ȁB |
| 5��2���i�j��������f�v |
��S��̊|�I�P�艉���ߕt���ė����B�U���R���i�y�j�P�W�F�S�T�J���A�|��s���U�w�K�Z���^�[�z�[���B���ꗿ�P�O�O�O�~�B�Ȗڂ̓��b�V�[�j�u�Z�r���A�̗����t�v���ȁA���[�c�@���g�u�s�A�m���t�ȑ�Q�R�ԁv�A�`���C�R�t�X�L�[�u�����ȑ�T�ԁv�B�w���͖ܘ_�䕐��搶�B�s�A�m��e���̂͊|��o�g�̍��c�āi���܂������j�N�ŁA���ݓ����|��t�����Z�݊w���̎㊥�P�U�B�V���p���R���N�[��in
Asia
��S���{�w�����y�R���N�[���Ȃǂŏ�ʓ��܂��ʂ����Ă����ނŁA�ǂ�ȃ��[�c�@���g�����Ă���邩�ƂĂ��y���݂��B�Ȃ��A�`�P�b�g�̂��p���͓����W�O�O�~�ŏ����Ă���܂��B
�S�[���f���E�B�[�N��������Ƒ����P��́u�ܗ��v���h������A�艉�Ɍ����čŌ�̎d�グ�ɗ�ނ킯�����A�����̖�Ɏ���艉�́u�I�Ȉψ���v���J�Â����B�P�N�ɂP�x�����艉���J���Ȃ��|�I�P�c���ɂƂ��Ď������K�Ȃ͍ő�̊S�����B���́A�|�I�P�͊��̒艉�ɂ͂���R���Z�v�g�������đI�Ȃ��邱�Ƃɂ��Ă���B���s�s�̃A�}�I�P���A��s�s�̃A�}�I�P���悭���悤�ȋȂ�����Ă����݈Ӌ`�������B�B�ꂽ���Ȃ@�����킷�邱�Ƃɂ���Ēc���̌o���〈�����L�߂�ƂƂ��ɋZ�p�̌����}�낤�Ƃ����l�����B���݂ɑ�P��艉�̃��C���Ȃ̓����f���X�]�[�������ȑ�R�ԁu�X�R�b�g�����h�v�A��R��̓t�@�����́u�O�p�X�q�v�i����ɂ͋�J�������y���������I�j�������B
����̃R���Z�v�g�͓�A�u�h�C�c�ƃ��V�A���������v�Ɓu���̃A�}�I�P���]��̂�グ�Ȃ����ȁv�ł���B���{�͓`���I�Ƀv���I�P���܂߂ăh�C�c���y�Ώd�ŁA�h�C�c�E�I�[�X�g���[�n�̉��y�����t�ȑS�̖̂�W������߂Ă��邵�A���V�A��i���������̂̓`���C�R����������肾����B
���āA�c�����炱���̏����ɓK�����Ȃ��W�����Ƃ���A�o���o���B���Ȃ͈ȉ��̒ʂ肾�B
�y�P�v���z�@�S�������̂��߂̃p���@�[�k�i�����F���j�A�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�ȁi�h�r���b�V�[�j�B���[�}�̎ӓ��Ձi�x�����I�[�Y�j�C�D��Ŋ����I�ȃ����c�i�����F���j�D��z�Ȃ��u�Ղ�v�i�h�r���b�V�[�j�E�L���[�o���ȁi�K�[�V���C���j�F���x�g�ȁi�o���g�[�N�j�G�Q�̉f���i�o���g�[�N�j�H�n���K���[�̕��i�i�o���g�[�N�j�y�Q�v���z�@���E���@���X�i�����F���j�A�N�[�v�����̕�i�����F���j�B���g�ȁi�h�r���b�V�[�j�C�f�B���F���e�B�����g�i�o�[���X�^�C���j�D���[�}�j�A�������ȁi�o���g�[�N�j�E���z���i�ۉȗm�j�F�G�j�O�}�ϑt�ȁi�G���K�[�j�G�̌��u�s�[�^�[�E�O���C���X�v����l�̊C�̊ԑt�ȁi�u���e���j�H�K�����^���ȁi�R�_�[�C�j�I�����Ⴍ�̎��ɂ��ϑt�ȁi�R�_�[�C�j�y�R�v���z�@�nj��y�̂��߂̋��t�ȁi�o���g�[�N�j�A�����ȓ�Z���i�t�����N�j�B���v�\�f�B�[�E�C���E�u���[�i�K�[�V���C���j�C�勬�J�i�O���[�t�F�j�D�}�E���[���E���A�i�����F���j�E�����̎ӓ��Ձi�T���E�T�[���X�j�F�����ȑ�P�ԁi�r�[�[�j
�G���[�}�́u�����v�u�Ղ�v�u���v�i���X�s�[�M�j�H�����ȑ�S�ԁu�s�Łv�i�j�[���Z���j�B
�������Ă݂�ƃh�C�c�E���V�A���ȊO�ɂ���R���Ȃ�������ˁ[�B�p�������Ȃ���m��Ȃ��Ȃ����\���邩��f�v���ɉ₩�����Ȃ�����I�ŏI�I�ɂǂꂪ�I��Ă����N�̒艉�͖ʔ����Ȃ肻�����B |
| 4��27���i�j�~�����萰�ꂽ�� |
 |
| �u�P�Q�ƌ��ݎg�p�̃V���g�C���[�r�W�O�O�i�E�j |
�Ƃ��Ƃ����C�X�^�[�̎d�|�������������I�z���c����ł���n���v�l�̂��A���B�ޏ������C�X�^�[�̃N���j�b�N�Ŏ��ɒ��ڊm�F�����Ƃ���A���[�h�͂�͂胔�@���h�����̂u�P�Q�i�┠�j�ŁA�d��N���ł͂Ȃ����ʂ̂a��Ǘp���������B���݂Ƀ}�b�s�̓����c�@�[�i�i�ԕs���j�ŁA�n���v�l���x����������Ŏt�������c�F���c�P�������o�[������C�肵���J�X�^�����炵���B
���āA���̕��đ����u�P�Q�̂R���w�����A���݈��p�̂f�R�ɕt���Đ����Ă݂�ƁA�Ȃ�قLjӊO�ɂ������Ɩ�ł͂Ȃ����B���[�h��[�̕����h�C�c�Ǘp������P�����L���̂ŁA�}�b�s����͂ݏo���Ă��܂����������A���ʂ͖��炩�ɑ�������B���̑��艹�F�͂�▾��߂ƂȂ�A���Ƀs���p�����悤�ȃx�[���I�������͂��Ɋ�������B��ԋC�ɂȂ����̂́A���[�h�����L�������������������������Ƀ��[�h�������悭�U�����Ȃ����߁A�������������̗����オ�肪���x��邱�ƁB
�����A���C�X�^�[�̂悤�Ɍ����Ė������������A�S���悤�Ɋy���炷�������ɂ͂҂����荇���Ă���̂��낤�B�܂��u���͂��ꂢ�������ʂ�����Ȃ��v�Ƃ����O��̐��ɑ��Ă��L���ɓ����͂����B���C�X�^�[�̉��≉�t�X�^�C�������̏�Ȃ��D���Ƃ����l�Ȃ玎���Ă݂Ă͔@�����낤���B
�Ȃ��A���[�h�Ɋւ��Ă͍ŋ߂j����\����T���v������������e�n�f�k�h�d�s�s�`�i�t�H���G�b�^�H�j�Ƃ����h�C�c�̃��[�h���f���炵���B���݃I�P��A���T���u���Ńe�X�g���Ȃ̂ʼn��ꌋ�ʂ����|�[�g�ł��邾�낤�B |
| 4��15���i�y�j�z�t |
 |
| ���͊NJy�툤�D�҂Ŗ��t��� |
�_�ސ�A�[�g�z�[���ŊJ�Â��ꂽ�u���c���R���t��v�ɎQ�������B���N�łP�O���N���}���邻�����B�ܘ_��������u���c�v�𖼏���Ă����킯�ł͂Ȃ��B200�P�N��12���ɂ�͂蓯���A�[�g�z�[���ŊJ���ꂽ��6��u���R���t��v�ɏ��Q�����A��Ɏ҂̐��R�~�搶�ɂ�����ĈӋC�����B���N����S���K�͂Łu���R���t��v��W�J���邱�ƂɂȂ����̂ŁA�u���R���t��v���˂̒n�A���̉��l�́u���R���t��v���u���c���R���t��v�ƌĂԂ��Ƃɂ����̂��B�ȗ��S���e�n�ŊJ�Â��ꂽ�u���R���t��v�͂P�P�T���𐔂��A���Q���҂͗T��2���l���Ă���B���N�́u���c�v�Q���҂͍�N��200�l���X�ɏ���A�q�Ȃ��Ԃ��Ă����肫��Ȃ����������B
 |
| �O�����ŎQ���������b�L�[�r�c���� |
���āA���n�[�T���������Ȃ�̍��A1�l�̒j�����O����������ē����ė����B���܂Ŕ��i�ŎQ�������l���������A���������l�T���X�E���R�[�_�[�̃O���[�g�o�X�ȂǂƂ����g��`�ɕ������Ȃ��h�y��������Ă���悤�ȕς��҂��K�����l������̂œ��ɋ��������Ȃ������B7�N�Ԃ�ɃN�����l�b�g���P�[�X����o���Ă����Ƃ����ׂ̏����Ɓu���̐l�A���b�L�[�r�c�Ɏ��Ă܂��H�v�ȂǂƘb���Ă�����{���ɓ��l�������i�B
���ł��s�a�r���W�I�̃��C�u���^�ɗ����̂������ŁA�����̉��t�ȁu�W���p�j�[�Y�E�O���t�B�e�B�v�̒��Łu���ˉ���v�̃����f�B���O�����Œe�����Ƃ���������B���b�L�[����͑S���̎O�������S�҂������ŁA���n�[�T���ł͂���Ȃ�ɒe�������̂́A�{�Ԓ��O�ɂ͖T���猩�Ă��Ă��C�̓łȂ��炢�オ���Ă����B�Ă̒�A�{�Ԃ̃\���łƂ���܂��������ǁA�܁A������p���āu���R���t��v�炵���Ă悩���������B |
| 4��11���i�j�t�J |
 |
| �N���Ɗy���͏�ɗՐ�Ԑ� |
����a�������}�����̂��@�ɁA���N�����߂Ă����v�������������s�Ɉڂ����B�X�P�[���ւ̒���ł���B�T�����[�}�����Ƃ܂ł̎c��Q�N�ԁA�܂�Q�S�����łQ�S�̒����}�X�^�[���悤�Ƃ�������ȁA����I���Ȍv�悾�B�������ӁA�Z�����ԂȂ��瓯�����̉��K�╪�U�a�������炤�킯������A�P������ɂ͂��̒��̃X�y�V�����X�g�ɂȂ�i�͂����j�B�X�P�[���̓A�C�q���[��O���E�T�����͂��߂R�A�S���͎����Ă��邯��ǁA��������Ȃ����ǂ���V�i���l���B������ŏ��ɋ�������V��搶���u���K�ȂȂ̒��ŏo���������v�Ƃ̂��܂�ꂽ�̂ŁA�����ǂ����Ƃɍ��܂ŃX�P�[�����܂Ƃ��ɂ���������Ƃ��Ȃ��B�u�Ȃ̒��ŏo����ɂ̓X�P�[������邵���Ȃ���v�ƌ�����̂͂��ŋ߂̂��Ƃł���B
�ǂ̃X�P�[���{�ɂ��邩�H�Y���ɑI�̂́A���ē��R�m�搶���烌�b�X�����Ă������ɍw�������J�[���E�x�[���}���B�ÐF���R�Ƃ��������̒��ɉ������ƈ퉹�y�̓`�������Ղ��Ă���悤�ȋC�����邵�A�x�[�����������������͋C�t���Ȃ��������A�y����Ƀh�C�c�ǂ̎w�g���������Ŏ�����Ă���̂ŁA�G�[���[�����ɂ͂ƂĂ����ɂȂ�B
���āA�R���V��ɂȂ�Ȃ��悤�Q�̍��𗧂Ă��B�P�́A�T�{��h�~�p�Ɋy���Ɗy����x�b�h�̉��ɃZ�b�g���Ă������ƁB�Q�ڂ́A��ԓ��������n�߂邱�Ƃ��B�������Ȃ�R�ɓo���茯�����R�̏ォ�牺��Ă�������y���낤�Ƃ�������ȗ����ł���B������V�A��V�̃X�P�[����{�����̂����A�A�A�����B
 |
| �{���̉d�֒����͕σg�����i��U�j�Ɠ������K���B������cis��dis������炵�� |
�U�͂���̂ɂV�͂Ȃ��B�A�C�q���[�����l���B�m�����w�Z�̉��y�̎��ƂŁ�̐��̓g�j�C�z���w�n�A��̓w���z�C�j�g�n�̏��ő�����ƏK�����͂��B�d�n������σn���������Ă���͂��Ȃ̂����A���ĉ��ŁH�ƁA�����ŔY��ł��Ă���肭�͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����͎�肠������U�̂e����
dur ���牺�R���J�n���邱�Ƃɂ����B
|
| 4��5���i���j�����J |
 |
| �Ђ�����炢�Ă�����Ă������ |
����d���ꂽ���ɂ��ƁA�J�[���E���C�X�^�[���ŋߎg���Ă��郊�[�h�̓��@���h�����u�P�Q�i�┠�j�̂R���������B���@���h�������g���Ă���Ƃ͕����Ă������A�Ă�����h�C�c�Ǘp�̃z���C�g�}�X�^�[���Ǝv���Ă����B�t�����`�p�̂u�P�Q�Ȃ�}�b�s����͂ݏo���Ă��܂��ł͂Ȃ����A�ƒN�����v�����A���Ƃ���̓G�X�N���p�I���Ƃ����B�Ȃ�قǁA�m���ɃG�X�N���p�Ȃ烊�[�h�̕������傤�ǃh�C�c�}�b�s�ɍ��������m���ȁB�l�͕ʂɃ��C�X�^�[�t���[�N�ł͂Ȃ����A������Ǝ����Ă݂鉿�l�͂��肻�����B
�Ƃ�����ŁA�����l���X�ɏo�����u�P�Q�̃G�X�N���p���[�h�����]�����̂����A���ʂ̐��Ȃ炠�邪�u�P�Q�ł͏o�Ă��Ȃ��ƌ����B�J�^���O�܂Œ��ׂĂ���������玖���Ȃ̂��낤�B���Ƃ���Ƌ┠�̒��g�͕��ʂ̂a��Ǘp�������̂��낤���H�u�┠�̂R�v�Ɓu�G�X�N�����[�h���p�v�͂ǂ�������Ȃ�m�x�̍������Ȃ̂��B
���C�X�^�[�͍��N�����������Ō��J���b�X��������悤������A�N�����ږ{�l�ɕ����Ă݂Ă���Ȃ����B |
| 3��19���i���j�t��ԁH |
 |
| �����V���I�[�v�������l���X |
��������ł���B���x�͂i�q�l���w�O�̒b�����ɂ��铖�Еl���X�̐V���I�[�v���ɔ����A���ĕl���X�ƍ��͖����l���x�X�ɍݐЂ����Ј��ɌĂт�����������B�l���x�X�͑S���ōł������Ȏx�X���������A���̍ŏ��̕��C�n�ł���A�T�����[�}���l���̑�P���ݏo�����v���o�[���ꏊ�ł���B
���̓�����͐��N�ɂP�K�͂ɊJ�Â���Ă������A�����o�[�̒�����R�N�ȓ��ɑ�ʂ̒�N�ސE�҂��o�邽�ߍ��Ō�ɂȂ邾�낤�Ƃ̂��ƂŁA�Q�O�O�l���̉��������炪�W�܂�A���������łR�O�N�U��̍ĉ����э����������オ�����B
 |
| �X�������H���Ă̕s�ǎЈ��B |
��X�c��̐��オ���Ђ������a�S�V�N���̓I�C���V���b�N�̒��O�ŁA�܂����x�������̑����ɂ���������A�x�X���̕��͋C�����ɂ̂�т肵�����̂������B������p�\�R�����d���[�����������ゾ�B���X���ɒ��炪�I���ƁA�Ј����Ǘ��E���߂��̋i���X�ŃR�[�q�[�����݂Ȃ���V����ǂ萢�Ԙb�����Ă���A�����ނ�Ɏd���ɏA���Ƃ����̂����ۂ������B
 |
| �����̊F����J�l�ł����I |
��������b���邪�A�ʐ^�̂S�l�g�́A�ȑO�����Ɛg���ŐQ�N�������ɂ������F�ŁA����̌�b�s�A�i�V�[�E�e�B�[�E�}���j�j�Ƃ����u�����v���g���ĂQ�K�̊y�������ŗ��������A���̓��̃T�{�����ł����킹�����̂��B�b�s�Ƃ͂b��������e
�s������ �̈Ӗ����B�悭���̎؉ƂɊe�X�Зp�ԂŏW�����Ă͒��Ԃ��疃���ɋ��������̂������B������A�x�O�̐����ɓ������牽�ƁA��i�A������ɑ���͂�ł����Ȃ�Ă��Ƃ��������i�B�ܘ_�������̂���߂��Ȃ��������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B����[�A���̍��͊y���������ȁ`�B |
| 3��15���i���j�t�旈�� |
�T�����[�d�@���o�c�s�U�ő僊�X�g�����炵���B�̂��牽�ƂȂ��T�����[���ۛ����Ă����̂ł�����Ǝc�O���B������ꗬ�u�����h�Ǝv���Ă����킯�ł͂Ȃ����A�T�����[���i�͈�������Ɏg�����̗���ɂ����Ă悭�l�����Ă���B�̎g���Ă���������͐��̗e�킪�Ԍ������h�ȃK���X�ŏo���Ă��āA���̎c�ʂ���ڂŕ������ɃC���e���A�Ƃ��Ă��D�ꂽ���`�������B���̉����킪�������I��������K���X�̗e�킾���͎̂Ă������A������֑}���̉ԕr�Ƃ��Ďg���Ă����قǂ��B
 |
 |
| ������^���N���X�P���g�� |
�X�^���h�ɂ��Ȃ�t�r�a�[�q |
���ݎg���Ă���X�`�[���A�C�������T�����[�����A�ŋߔ������h�b���R�[�_�[���T�����[���B���̃��R�[�_�[�̗D�ꂽ�_�́A�R�[�h�ނ�f�B�A���g�킸���ڃp�\�R���̂t�r�a�[�q�ɐڑ����Ę^���f�[�^����荞�߂邱�ƁB�����[�J�[������F�X�o�Ă��邯�ǂ���Ȃ̂͑��ɂȂ������B���i���荠���������^���̉������X�ǂ��B�T�����[�͂ƂĂ��ǐS�I�ȃ��[�J�[���Ǝv�����ǁA�Ⴆ�Ήt���̃V���[�v�Ƃ������̃\�j�[�Ƃ��̔��̏����Ƃ����������D�ʗ͂��ア�̂ŁA�������p�̒ቿ�i���i�ɃV�F�A��D���Ă��܂����̂��낤�B���ӂ̃\�[���[�Z�p��������Ă��ɂ��Đ����������Ԃ��ė~�������̂��B�撣��A�T�����[�I |
| 3��2���i���j���{�A������ |
 |
| �͂ɂ��ޏΊ炪���킢����t�� |
3���ԃC���h�l�V�A�̃W���J���^�ɏo�������B�C���h�l�V�A�͏��߂Ă������̂Ŋ���̃T�v���C�Y���������B�܂��A�s���͐l�ƃN���}�̑�^���B��ʃ��[���͖��������R�ŁA���s�҂̓N���}�̐�ڂŎ��R�ɉ��f���A���т����������̃o�C�N�������悤�ɃN���}�̊Ԃ�D���đ���B�N���}�̍����n�_�ł͉��ɕ@���˂�����ŗ��邩���Ȃɏ���Ă��Ă��n���n�������ςȂ����B�������u����A�Ԃ���I�v�Ɗo�債�Ă��s�v�c�Ȃ��ƂɐڐG�P�O������O�łǂ��炩��Ƃ��Ȃ��u���[�L���|���Ď~�܂�B�N���N�V������{�����߂����ɕ����ꂸ�A�ǂ̃N���}�ɂ����݂⏝�͌������炸�A���̂�ڌ��������Ƃ���x���Ȃ������B�C���h�l�V�A�Łu���݂̌ċz�v�Ƃł��ĂԂׂ����H���̗D�ꂽ�^�]�Z�p�ƐÂ��Ȃ�R�~���j�P�[�V�����\�͎͂��Ɍ����ƌ����ق��Ȃ��B
 |
| �z�e���ɗאڂ��Ă����C�X�������@ |
�z�e���ɔ��܂��Ă��ĎQ�����̂́A����4�����ɂȂ�ƕ������Ă���剹�ʂ̂��F��B�����̑唼���C�X�������k�ł��邱�̍��ɂ́A���������ɃC�X�������̎��@������A���̓��̎l���ɐݒu���ꂽ�X�s�[�J�[���痬�����̂����A�E���̊X��Ԃ��Ȃ���̑剹�ʂŁA���_�_�҂ɂƂ��Ă͒P�Ȃ�����W�Q�̑������B���������̐����i�H�j���ςɉ��K�ɂȂ��Ă���̂ŁA�Q�ڂ��Ȃ�������\���t�F�[�W�������Ă��܂��B1���ڂ̓h�E�~�E�t�@�E�\�łȂ����u���҂̍s�i�v�̏o�����Ɠ������ȁ`�A�Ƃ��A2���ڂ̓~�E�\�E���E�h�ŁA���{���w�Ɠ����l���������K���ȁ`�A�ȂǂƞN�O�ƍl���Ă�����ɂƂ��Ƃ����X�Ɩ邪�����Đ����s���ɂȂ��Ă��܂����B
 |
| �P�O�����s�A�D�ł���P�Q�O�O�~ |
�C���h�l�V�A�̒ʉ݂̓��s�A�����A���W�r�㍑�̂������ɂ��ꂸ�C���t�����i�s���Ă���̂ŁA�Ƃ�ł��Ȃ��P�ʂɂȂ��Ă���B��ԍ����������P�O�����s�A�A����5���A�Q���A��Ƒ����̂����A�~�Ɋ��Z����ɂ͂P�O�O�Ŋ����ĂP�D�Q���|���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���n�ŐH�������āu�V���T�烋�s�A�ł��v�ƌ���ꂽ���ɂ͈�u�тт������A���͐�~�ɂ������Ȃ��̂��B���̋ɒ[�ȉ��i���ɂ͌��n�̒��݈��������Ɍ˘f���悤�ŁA�ʉݒP�ʂ��ԈႦ��ƂƂ�ł��Ȃ����ƂɂȂ�B�u���H�������̂R���H�ȁ[�A���s�A����Ȃ��ĉ~�ł���[�A���H�h���H������ς����I�v�Ƃ����悤�ȉ�b���펞���킳��Ă����B |
2��14���i�j�t���������ȁH
|
 |
| ���̃W���C���g�E�R���T�[�g�̃|�X�^�[ |
�Q�O�O�Q�N�U���A�|��s�ɓ����ɒa�������u�|��s���I�[�P�X�g���v�Ɓu�|�쐁�t�y�c�v�̏��̃W���C���g�E�R���T�[�g�����j���ɐ��U�w�K�Z���^�[�E�z�[���ŊJ�Â��ꂽ�B�s���V�|��s���̊̐���Ŏ����������t����Ɏs���̎��O�o�q�����S�ŁA��l����z�[���͂قږ��ȏ�ԁB��P���́u�|���v���A��Q���͉�炪�u�|�I�P�v���A���ꂼ��S�Ȃ����t�B�����đ�R�������悢�捇�����t���B�Ȗڂ̓��O�i�[�́u�j�������x���O�̃}�C�X�^�[�W���K�[�O�t�ȁv�ƁA�G���K�[��ȁu�Е����X�v�B�ꏏ�ɍ��킹��@��͂R���Ȃ��������A�ǂ���ɂƂ��Ă�����m�����閼�Ȃ��������A���܂��̂Ȃ����݂ŁA���獇�킹�Ƃ����ǂ��Ӗ��ْ̋�������`���Ă��A�{�Ԃ͑����҂����荇���傢�ɐ���オ�����B��搶���U�����I�ȁu�Е����X�v�͉��t������肪��~�܂��A�A���R�[���Ƃ��Ă�����x�R�[�_��M�������Ƃ��떞�ꊄ������̔��芅�тƂȂ����B���̐����ɋC���悭�����H��Î҂ł���|��s���U�w�K���ƒc����A�I���コ��������Q��W���C���g�E�R���T�[�g�����N�̂P�O���ɂ�肽���Ɛ\�����ꂪ�������B�s����Â���C�x���g�ɏo������ƁA�����̎s���ɉ��t���Ă��炦���ɕ⏕���܂ł��炦��̂ŁA�m�o�n�^�c����叕����ł���B
 |
| �}�c�P���T���o�Ő���オ��|���_���T�[�Y |
���āA���y�c�̒c���������[���Ȏ育�����Ɩ������𖡂킢�A�݂��̌������]���e�r��}��ׂ������ł��グ��ɗՂB���̂����肩�琁�t�y�c���Ɗnj��y�c���̃����^���e�B�[�̈Ⴂ�������ɂȂ��Ă���B������|���̒c���̕������|�I�ɎႢ�B�Ⴆ�g�����y�b�g�𐁂��Ă���q���P�X�������肷��B����Ɂu���R���t��v�ł͑̌��ς݂����A���|�I�Ƀm�����悢�I�������ݎv�Ăő�l�����|�I�P�c���ƈႢ�A�J���I�P�}�C�N�������Ă���̂͏�Ɋ|���̏����c���B�������B�U��t���̃s���N���f�B�[�E���h���[��A�|�I�P�j���ւ̃f���G�b�g���v�i�l���u�������v���S�킳�ꂽ�j�Ȃǂ͏��̌��ŁA���ɂ̓e�i�[�E�T�b�N�X�S���̒c������Ɓu�|���_���T�[�Y�v�̈�c���X�e�[�W��苒���ă}�c�P���T���o��x��o���ɋy��ŁA���N�Ə��V�������|�I�P�c���͊��S�Ɍ��t���������̂������B
���`�ށA���t������ׂ��B |
| 2��4���i�y�j�ǂ������t����`�I |
 |
| �L�����o���͌��\�������� |
�����N����ƃR�[�q�[����t���ނ̂���ۂɂ��Ă���B���Ԃ��Ȃ��̂Ńh���b�v���̃C���X�^���g�Ȃ̂����A���R�����܂�����Ȃ肾�B�u�����E�J�t�F�v�����߁A�t�b�b�A�h�g�[���A�L�C�E�R�[�q�[�ȂǐF�X�Ǝ��������ŁA�L�����o���E�R�[�q�[�̃h���p�b�N�E�R�[�q�[�Ƃ����̂���ԋC�ɓ����Ă����B����͑g�ݗ��Ď��̃h���b�p�[�ƃR�[�q�[�����ʁX�ɂȂ��Ă��āA�A���~�̑܂��J���ĕ������o���̂ŁA����□�����̂��̂��V�N���B
�Ƃ��낪�A����S�N�Ԃ�Ƀz���c�̗��K�Ɋ���o��������̃��L�����A�����Ő������Ƃ����R�[�q�[������������B�Ȃ�ł���������������w�����Ė��������ɖv�����Ă���̂��Ƃ��B�u��������Ă���Ɛ悸�C�`�n�[�������ł���B�ł��A���̂��Ƃ̔����ȃj�n�[�������Ȃ��悤�ɂ��Ȃ��ƃ^�C�~���O���킵�܂��B����������������͈�Ӓu����������Δ��������ł��A�A�A�]�X�v�Ӂ[��A�������J���[�݂������ȁB�Ƃɂ������̓��̓e�J�e�J�ƍ����肵�Ď��ɍ��肪�ǂ��B�ǂ�Ȗ������邩�y���݂��B�����|��ɖ߂��Ĕ��������R�[�q�[��_�Ă悤�I�Ǝv�����̂����A�A�A�B
 |
 |
 |
| �܂��d���~�����܂��� |
���퐻���e��������܂��� |
���C�ɓ���̃}�O�J�b�v�ł� |
�l���Ă݂��瓤��҂��~���������B�ȑO�����Ă����蓮�̃~���͍s���s���B�����ŋ߂��̓d�C�X�œd���̂��̂��ė����B���ĂƎv������A���x�̓t�B���^�[���h���b�p�[���������ƂɋC���t�����B���������{���đS�Ă������A���߂ă��L���������R�[�q�[�������ɂ̓x�X�g�ܖ����Ԃ��Q���قlj߂��Ă������ǁA���ɃR�N�������Ė����[���B����ł��Č��̒��ɋꖡ���c�炸�A�T���b�Ƃ��Ă���͕̂s�v�c���B�܂����̗ʂ�҂����ׂ̍����A�����̉��x�␂�炵���ɂ���Ė��Ƀo���c�L�����邯��ǁA�����������������̓��̖����ő�������o���悤�ɖ����w�͂��Ă݂悤�B
|
| 1��24���i�j�����Ԃ�Ԃ� |
�ُ�Ɋ����~�̂����ŁA���N�͕����̃V���[�v���Z���~�b�N�E�t�@���q�[�^�[�ɐ������b�ɂȂ��Ă���B�������g�����������������u���̏Ⴕ�Ă��܂����B���i�Ȃ畔���̎��x���T�O���ȏ�ɕۂ����̂ɁA���������R�O���O��ɂ����オ��Ȃ��B
 |
| �オ�V�i�̉����t�B���^�[ |
�w�����ĂS�N���o�̂ɉ����t�B���^�[�𐴑|�������Ƃ����ւ������Ƃ��Ȃ������̂ŁA���o���Ă݂�Ƃ�͂�ꌩ���ă{���{����ԁB���ẮA���ꂪ�������H�ƁA�߂��̗ʔ̓d�C�X�ɒ������ĐV�i�Ɏ��ւ������S�����ʂȂ��B�����ŁA�w�ʂ̉����g���[�������o�����ꂱ�ꕪ�����Ă݂�ƁA���̕��ɏ����Ȑ��Ԃ̂悤�ȕ��i���t���Ă���B�ǂ���炱�ꂪ��]���ăg���[�ɗ��߂����������t�B���^�[�ɋ��ݏグ�Ă���炵���B�G�ꂽ�t�B���^�[�ɔM���𐁂����Ď��x���グ��d�g�݂��B
�����A���i�͐����ɖv���Ă��ĊȒP�Ɏ��O�����o���邱�̏����Ȑ��ԃ|���v�́A��̉��͌��ɂ��ĉ�]���Ă���̂��낤�H�ǂ��l�������点�Ă������ł��Ȃ��B�����ŁA���ߌ��ŃV���[�v�̃z�[���y�[�W���炨�q�l���k������{�����āA���[���Ŏ��₵�Ă݂��B����Ɨ��������Ԏ������āA�̏�̂��l�тƂƂ��Ɉȉ��̂悤�Ȑ������������B�u�����|���v�͎��̌����ʼn��A�{�̓����̓����ʒu�ɂ�������[�^�[������܂��B���ꂪ���Ǝ��͂ŋ����|���v�����悤�ɂȂ��Ă���܂��B���̂��ߋ����|���v�ɐ��C�Ȃǂ����ďd���Ȃ�ƁA���ɂ����Ȃ�܂��B�A�A�A�v�Ȃ�قǁI���Ƃ��������ȉA�����ĉ��Ɗȕւɂ��ē��̗ǂ��d�|�����낤�I���[���ɂ͋����|���v�̕i�Ԃ≿�i�i�P�C�U�O�O�~�j�܂Ŗ��L����Ă����B�P���ɂ���������V���[�v�E�t�@���ɂȂ����l�́A�������i�𒍕��������Ď��t�����B���̂悤�ɐ����ǂ����悤�ɂȂ����|���v�̂��A�ŁA�ȗ������̎��x�͉��K�ɕۂ���Ă���B
 |
 |
 |
 |
 |
| �����g���[�������o�� |
���������t�B���^�[������ |
�g���[�̋��ɏ����ȕ��i�� |
�E���V�i�̋����|���v |
���̐��Ԃ����͂ʼn�]���� |
|
| 1��13���i���j�����a�炮 |
�u�r�o�`�l�v�͈ĊO�g�߂ȂƂ���ɂ������B���H�ȗ��A���ӂɂr�o�`�l��m���Ă��邩�H�ƕ����Ă���̂����A�u�����A��^�̃X�[�p�[�Ȃ甄���Ă܂���v�Ƃ��u����A���\������������v�A�u�F��Ȏ�ނ������ˁv�ȂǂƁA�ƂĂ��F�m�x�������̂��B
�l�͐���v�������Ȃ��R���ɂ���h���L�z�[�e�̐H���i�����Ŕ��������B�z�[�����Ђ̃z�[���y�[�W�̎ʐ^�Ƃ�������ȁi������O�����j�r�o�`�l�ɑΖʂ������͂�����Ɗ��������B�e�ׂɌ���ƁA���{��\�L�̃��x�����\���Ă������肵�āA�O���[�o���ɔ̔�����Ă��邱�Ƃ��������킹�Ă���B���������Ď��H�ɋy���A�A�A��[�A�X�p�����[���̈Ӗ��������������悤�ȋC�������B
 |
 |
 |
 |
�W���J����ƃR�[���r�[�t�ɋ߂�
�����ƂƂ��ɁA�����\�[�Z�[�W
�̂悤�Ȃ��̂���������ł��� |
�ʂ��t���ɂ��A�@������h��������
��J���ĎM�̏�Ɏ��o���ƁA
���ɔ����ۂ��_�炩�����̉� |
���ŐH�ׂ��炵����ς��ė]�����
�����Ȃ������̂ŁA�t���C�p����
�u�߂��炸���ƐH�ׂ₷���Ȃ��� |
�萻�X�p���E�G�b�O������Ă݂���
����肢����Ă��Ă��_�炩���܂�
�̐H�����ǂ����Ȃ��߂Ȃ����� |
|
| �Q�O�O�U�N1��6���i���j�₽�犦�� |
���U�ɂܗ��̃`���y���Ŋ|�I�P�̃����o�[�Ǝ����y�����t���������A�����̎��ƂɋA�����B�����e���r�͂ǂ���܂�Ȃ����A�ߏ��̓X���قƂ�ǂ���Ă��Ȃ��̂ł������Ԃ����ė]���Ă��܂����B����Ȏ������C�V�����ɂł��s���ă}�E�X�s�[�X����������I�Ԃ��[�A�Ɠd�b�����Ă݂����u�U������c�Ƃł��v�Ƒf�C�����e�[�v������Ă���i���̐��́�������ȁj�B�܂������}�n�̋���X������Ă͂��܂��Ɠd�b��������ƁA���ꂪ�ӊO�ɂ�����Ă���Ƃ����B����X�Ƃ����Ƃ���̓h�C�c�N�������ɂƂ��Ă͑S�����͂̂Ȃ��X�Ȃ̂����A�y���Ɗy�������͏[�����Ă���̂ʼnɂɖO�����ďo�|�����B
�R�K�̊NJy�프���̉��ɃK���X����̃��y�A�E���[��������A���C�Ȃ�����`���ƏC�������Ă����Ⴂ�����C�t���āu�������p�ł��傤���H�v�Ƃ����悤�ɔ��݂������B���̏Ί炪�ƂĂ����R�őf�G�������̂ŁA�������C�ɂȂ��Ă����a��ǂ̊���ɂ��đ��k���Ă݂��B�u�����ǂɂЂт������Ă��Đ����x�ɍL��������A�k�肵�Ă邯�ǂق��Ƃ��đ��v�H�v�ޏ��͏�ǂ���ɂƂ��Ďe�ׂɊώ@����ƌ������B�u����͂����P�O�����ʂ���܂����A���̃g�����L�C�̍����ɂ��R�����������Ă܂��B���̂܂܂ɂ��Ă����Ƃ����ƐL�т邩������܂����B����ƈȑO������C�������Ղ�����܂��ˁv�l�͂T�����ʂ̊���Ǝv���Ă����̂����������̕��܂œ����Ă���炵���B������ӏ��͑S���C�t���Ȃ������B�Y��Ă������A�����ĂV�C�W�N�O�ɂ�����ďC���������Ƃ��v���o�����B
 |
| �ڂ��Â炵�Ă�����Ȃ��Y��Ȏd�オ�� |
��������ޏ��̌����ĂɊ��S�����l�́u�C�����Ăق������ǁA�Q�C�R���͊|�����ł���H�l�͖�����ɂ͐É��A��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƌ����Ɓu�������a���Ē�����Ζ����̗[���ɂ͎d�グ�Ă����܂��v�ƌ����B�ł́A�ƁA���łɏ�ǂ̃W���C���g�E�R���N�̌������˗����ė����҂��Ă���ƁA�S�����g�тɎd�オ�����Ƃ̘A�����������B�������ɍs���ƏC���̐Ղ��S������Ȃ��قNJ����Ɏd�オ���Ă����B�W���C���g�E�R���N�̌ł����œK���B�L�C�̍�����G�����������Ă��ꂽ�������B�C����̓g�[�^���P���T��V�T�O�~�B���[�Y�i�u���I�u���ۂɐ����Ă݂ĉ������v�u���ɋC�ɂȂ�_�͂���܂��H�v�u�܂����������Ή����ł��������������v�A�ޏ��̂��肰�Ȃ����t�������܂ł��l�̐S�����߂Ă��ꂽ�B |
|
|
 �N�Ɉ�x�̑S�����ł���u���R���t��Q�O�O�U�v���߂Â��Ă����B���T�Q�T���̓y�j���A�ꏊ�͍P��̉��l�����̈�فB�S�����͑������̂ō��N�łT��ڂ��B����͂Q�O�O�Q�N�A�Y����NK�z�[���ɂU�O�O�l�̘V��j�����W�܂��đ升�t���J��L�����B���̊������S���ɔg�y���đ��̍��I�ɒn�����J�Â����悤�ɂȂ�A�k�͖k�C�������͋�B�܂ŁA���݂܂łɂP�O�O��ȏ�A��Q���T��l�̉��Q���Ґ��𐔂���Ɏ����Ă���B�������݂̉��l�Ɉڂ����u���R���t��Q�O�O�R�v�ł͎Q���҂���l�ɒB�������̂́A���̌�u�Q�O�O�S�v�͂W�O�O���A��N�́u�Q�O�O�T�v�͂T�O�O���ƁA��⌸���Ă��Ă���̂͂��т������肾�B�n�������ꂾ������ɂȂ��Ă���A�킴�킴���l�܂ŏo�|���čs���K�R���������Ƃ������̂��낤�B
�N�Ɉ�x�̑S�����ł���u���R���t��Q�O�O�U�v���߂Â��Ă����B���T�Q�T���̓y�j���A�ꏊ�͍P��̉��l�����̈�فB�S�����͑������̂ō��N�łT��ڂ��B����͂Q�O�O�Q�N�A�Y����NK�z�[���ɂU�O�O�l�̘V��j�����W�܂��đ升�t���J��L�����B���̊������S���ɔg�y���đ��̍��I�ɒn�����J�Â����悤�ɂȂ�A�k�͖k�C�������͋�B�܂ŁA���݂܂łɂP�O�O��ȏ�A��Q���T��l�̉��Q���Ґ��𐔂���Ɏ����Ă���B�������݂̉��l�Ɉڂ����u���R���t��Q�O�O�R�v�ł͎Q���҂���l�ɒB�������̂́A���̌�u�Q�O�O�S�v�͂W�O�O���A��N�́u�Q�O�O�T�v�͂T�O�O���ƁA��⌸���Ă��Ă���̂͂��т������肾�B�n�������ꂾ������ɂȂ��Ă���A�킴�킴���l�܂ŏo�|���čs���K�R���������Ƃ������̂��낤�B